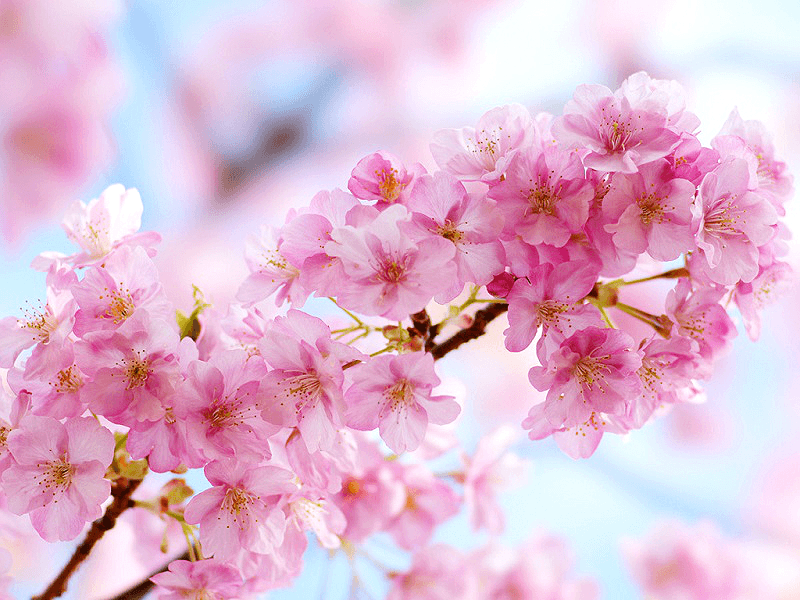日本では古の時代から、ある季節になると、老若男女を問わず村人全員が酒や食べ物を持ち寄り、風光明媚な山や海、温泉地などで大いに飲み食いしながら歌ったり踊ったりして存分に楽しむ文化がありました。
そのなかでも特に、春の風物詩・桜の花見はもっとも重要な行事とされていたようですね。

桜は農民のカレンダー
桜は昔の農民にとって、カレンダーのような役割を果たしていました。
2月頃、冬の寒さで目覚めた桜は、毎日の平均気温を加算していった"積算温度"が400℃前後になると花を咲かせます。農民たちは開花の状態を注視しながら、作物の種をまくタイミングを決めていたのだそう。
水田稲作が定着すると、それぞれの田んぼでいかに水を確保するかがもっとも重要な課題でした。上から下にしか流れない水を、すべての田んぼへ均等に行き渡らせるためにはいくつか必要なことがあります。
- すべての田んぼから一番高いところに、じゅうぶんな量の水源を確保する
- ひとつひとつの田んぼを水平につくる
- 水を張った上の田んぼから順番に田植えを行なう
稲作が広まるまで行なわれていた狩猟や焼畑式農業は、個人の能力に頼ることが多いですが、稲作は集団での作業。強力なリーダーによる強い結束が必須でした。
したがって、それまでの娯楽性や男女の出会いを重視した花見ではなく、その年の豊作を願いながら、村人たち全員の絆を深める行事としての花見が必要になったのです。
『万葉集』にみる桜
天皇から農民まであらゆる階層の人たちが詠んだ4500超の歌が記されている『万葉集』。そのなかにある1700首余りの歌で、およそ160種類の植物が詠み込まれています。季節ごとの花を愛でながら宴を楽しむ、日本人と自然の強い関わりが読み取れますね。
ただ、"桜"をテーマにした歌はわずか36首。"梅"を詠んだ歌が98首あるのに対し、約3分の1に過ぎません。ちなみに、一番多く登場するのは、"萩"で138首です。
さらに注目すべきことは、自然の中で咲いている満開の桜を見ながら恋人への思いを馳せる歌が多いこと。庭に咲く桜の花を楽しんだり、桜の下に大勢が集って宴をしたりしている様子の歌がないのは意外でしょう。
『万葉集』の中には、現代に生きる私たちが想像するような、明るく華やかな桜のイメージはほとんどありませんでした。
山峡(やまがひ)に 咲ける櫻を ただひと目 君に見せてば 何をか思はむ (三九六七)
〜山峡で満開に咲いている桜を、ただひと目あなたに見せることができたら、もう何の物思いもありません
あしひきの 山櫻花 ひと目だに 君とし見てば 吾戀ひめやも (三九七〇)
〜山に咲く満開の桜を、ただひと目だけでもあなたといっしょに見ることができたなら、私はあなたをこんなに恋しく思うことはないでしょう
一方で梅の歌は、春先に咲く花を愛でながら酒を酌み交わす場面が多いのです。
青柳(あおやなぎ) 梅との花を 折りかざし 飲みての後は 散りぬともよし (八二一 )
〜青く芽吹いた柳の枝と、満開に咲いた梅の枝を折って頭に挿し、じゅうぶんに酒を楽しんだら梅の花は散ってしまってもいい
青柳(あおやなぎ) かずらに折りし 梅の花 誰か浮かべし 酒盃(さかづき)の上(へ)に (八四〇)
〜青く芽吹いた柳の枝といっしょに頭へ挿した梅の花。それを、酒の入っている盃の上に浮かべたのは誰だろう
梅の花見から、桜の花見へ
『万葉集』が編纂された奈良時代の頃、農民は農耕儀礼に欠かせないものとして、"桜"へのこだわりを強めていきました。
ところが、唐時代の中国文化を教養のひとつとした貴族は、中国の詩文で多く歌われている"梅"へのこだわりこそが、貴族としてのステータスを示す必須の条件だったのかもしれません。
その後、衰退し始めた中国への遣唐使制度が廃止されて、唐文化の影響が弱まっていくと、平安貴族たちが平仮名を編み出し、『枕草子』や『源氏物語』などの日本文学が登場する時代を迎えます。その洗練された文化のなかで生み出された『古今和歌集』には、"梅"よりも"桜"が多く登場することから、多くの人が桜への関心を高めていったことがわかりますね。
次第に"梅の花見"は"桜の花見"へと変わり、花見における、農民文化と貴族文化の一体化が進んでいくのです。
<参考文献>
- 『花見と桜』 (白幡洋三郎/PHP研究所)
- 『万葉集にみる酒の文化―酒・鳥獣・魚介』 (一島栄治/裳華房)
- 『江戸川柳を楽しむ』 (神田忙人/朝日新聞出版)
(文/梁井宏)