古典落語に酒は欠かせません。落語の世界では、噺家(はなしか)が小道具として持つ扇子や手ぬぐいと同じように、重要なものとされてきました。
小道具はその見せ方によって、扇子が刀や煙管に、手ぬぐいが紙入れ(さいふ)や書物になるなど、観客がそれぞれの場面を想像する手助けとして必要不可欠。一方で、酒は義理人情、喜び、悲しみなど、江戸っ子の生きざまを赤裸々に語るために重要でした。
飲み過ぎには気を付けよう─「ずっこけ」
もう飲むのはやめようと思いながら、ずるずるといつまでも飲んでしまう酒飲みを"後引き上戸"といいます。
後引き上戸の男が「風呂帰りにちょっと1杯」のつもりで居酒屋に入りました。他の客が飲んでいるのを見ると、ちょっとでは物足りなくなってしまい、ついもう1本。しかし飲んでいるうちに、財布を持っていないことに気付きました。
ところがそれを言い出せないまま、ずるずると飲み続けてしまう。当然、店の若い衆が飲むのをやめさせようとします。
しかし、なんだかんだと理屈を言っては飲み続け、挙句の果てに大声で歌い出す始末。店の前には野次馬が集まってきてしまいました。
そこに、たまたまそばを通りかかったこの男の兄貴分。放っておくこともできないので、その店の勘定を払って連れて帰ろうとしました。それでもこの酔っ払いは道すがらに女をからかったり、小便の世話まで焼かせたり......さすがの兄貴分も腹に据えかね、ぐでんぐでんに酔っ払った男の襟首をつかみ、肩に担ぐようにして連れて帰る......つもりが、いつのまにか男の姿は消えて、着物だけになっていたのです。
慌てて引き返すと、途中の交差点に素っ裸で座り込んでくだを巻き、兄貴分を"追いはぎ"呼ばわりする始末。これには兄貴分も怒り心頭。男を家まで送り届けると「これが世話の焼き仕舞いだ」と、帰ってしまいました。
酔っ払いの女房は「しょうがない人だね。なかなか帰って来ないから心配したけど、それでもまあよく人に拾われなかったこと......」とぼやきます。
女房様が一枚も二枚も上手なのは、いつの時代も変わりません。
「火事と喧嘩は江戸の花」に象徴されるように、江戸っ子は男だけの世界になると勇ましく、そして格好良くふるまうもの。酒の勢いで怖いものがなくなる酔っぱらいも同様でしょう。「矢でも鉄砲でも......」と粋がりますが、酔いが醒めた途端、女房には頭が上がらなくなってしまうのです。
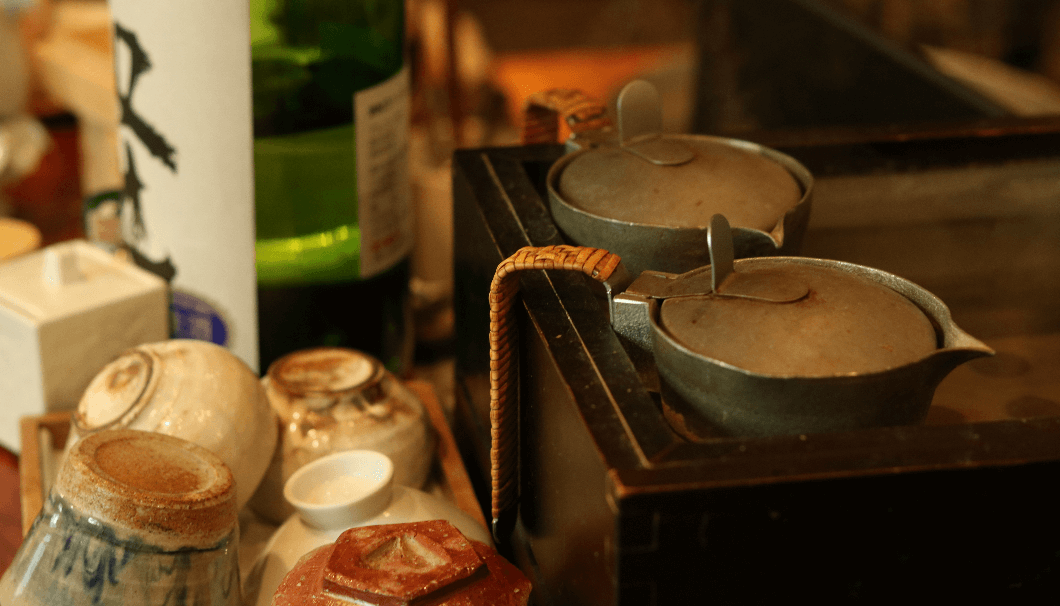
酒飲みの屁理屈
ある日、いつものように飲み友達が誘いにやって来ました。
「今晩、付き合わねえか。良い店を見つけたんだよ。今日は俺のおごりだからさ」
「いや、せっかくの誘いだけど駄目なんだ。今は酒が飲めねえんだよ」
「何だどうしたい。体の具合でも悪いのか」
「そうじゃねえんだけども。神様に、酒を断っちゃったんだよ」
「お前が?馬鹿だねこの野郎は。どうしてそんな無駄なことをするんだよ。お前ね、好きなものを無理に我慢するって、そっちの方がよほど体には良くないぜ。で、どのくらい断ったんだ?」
「向こう1年って約束なんだけどよ」
「1年も?何だなどうも、せっかく誘いに来たのに......あ、じゃあお前こうしろよ、向こう2年ってことにしてもらって」
「いやあ駄目だよ。向こう1年だって続くかどうかわからねえんだから、向こう2年なんてとても無理だ」
「だからさあ、向こう2年ってことにして、一晩おきに飲ましてもらうんだよ」
「なるほど!そういう手があったかあ。じゃあ向こう3年にして毎晩飲むかあ」
さすがの神様も駄目とは言えない、見事な屁理屈でありました。
◎参考文献
- 『落語にみる江戸の酒文化』旅の文化研究所 編/河出書房新社
(文/梁井宏)




