日本の旧暦で、"春の訪れの日"とされる立春。
冬至と春分の間に位置する立春の朝に搾ったばかりの新酒を、その日のうちに消費者のもとへ届けるという驚きのプロジェクトがあります。その名も「立春朝搾り」
2017年に立ち上げから20周年を迎えた当プロジェクトは、酒蔵と酒販店の間に立つ、株式会社岡永が立ち上げた「日本名門酒会」のミッションを象徴する活動のひとつです。
そんな「立春朝搾り」の魅力とは何か、プロジェクトを支える「日本名門酒会」とはどんな組織なのか、仕掛け人である株式会社岡永の飯田永介社長に話を伺い、その思いを紐解きます。
搾りたて生原酒の先駆け「立春朝搾り」20年の歩み
株式会社岡永は、1975年(昭和50年)に「日本名門酒会」を発足させました。日本酒の復興や、流通主導の日本酒専門店という業態の確立、消費サイドにおける日本酒の啓蒙を目指したこの会は現在、全国各地にある90の酒蔵、1,750の酒販店、情報や物流面で加盟酒販店をサポートする約20の支部卸で構成されています。
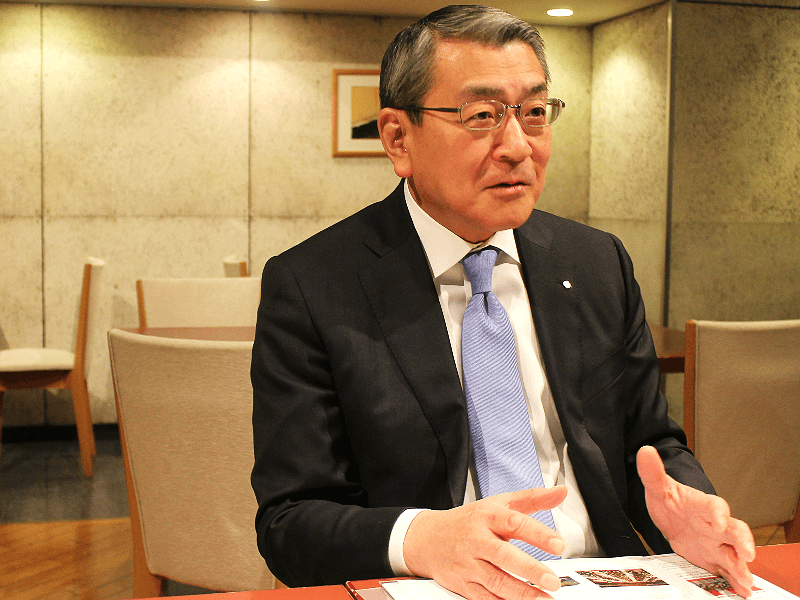
日本名門酒会が立春朝搾りのプロジェクトを始めたのは、今から20年前のこと。飯田社長が「日本酒の予約受注をいただける、記念日のようなものはないか」と考え、企画部長の森さんに何気なく相談を持ち掛けると、森さんはこう答えたそうです。
「予約受注をいただくには、立春しかありません。立春は旧暦ではお正月の前後にあたり、春の始まりを意味する森羅万象すべての生き物が動き出す日なので、新酒を売り始める記念日にはうってつけです。寒い時期だからこそ良い仕込みができるので、日本酒の味を考えても理にかなっているんです」
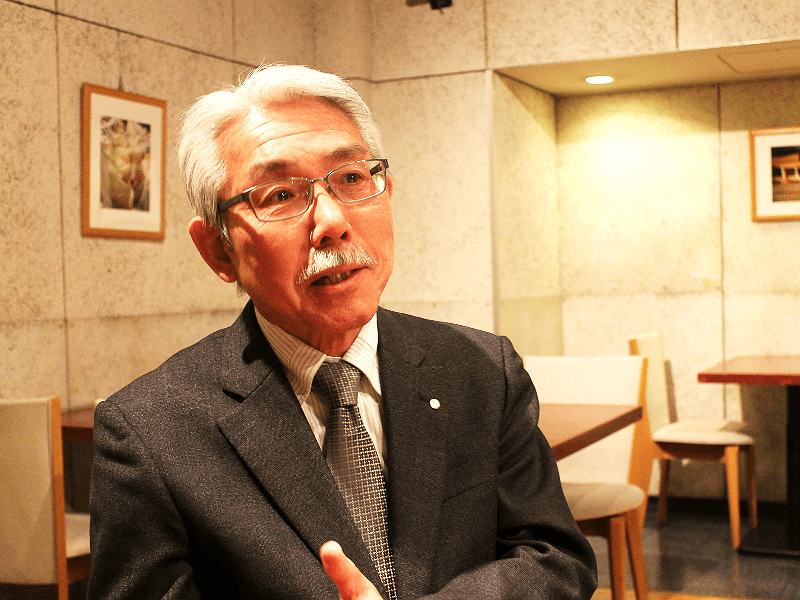
森さんの提案を聞いた飯田社長は、すぐにこのアイディアを採用。今や秋の風物詩として定着している「ひやおろし」など、数々の季節商品を仕掛けてきた日本名門酒会にとって、立春の日にお酒を販売することは、ごく自然な流れだったのかもしれません。
しかし、それだけでは訴求力が弱いと考えた飯田社長。"立春の朝に搾ったばかり"の日本酒を、その日のうちに飲んでもらうというアイディアを思いつき、「立春朝搾り」と名付けました。3年目からは、受け取り時にお祓いを行うことで、"縁起酒"としての地位を確立していきます。
今でこそ、火入れをせずに出荷する「生原酒」が多く流通していますが、前例のなかった当時は現場の動揺も大きかったと言います。
「始めた当初は特に大変だったと思いますよ。酒蔵は、立春の日の早朝にお酒を搾り上げ、酒販店の方たちも朝6時頃に蔵に集合するわけですからね。杜氏さんのなかには『酒蔵の"顔"である大吟醸酒を造るときよりも神経を使う』なんていう人もいました(笑)」
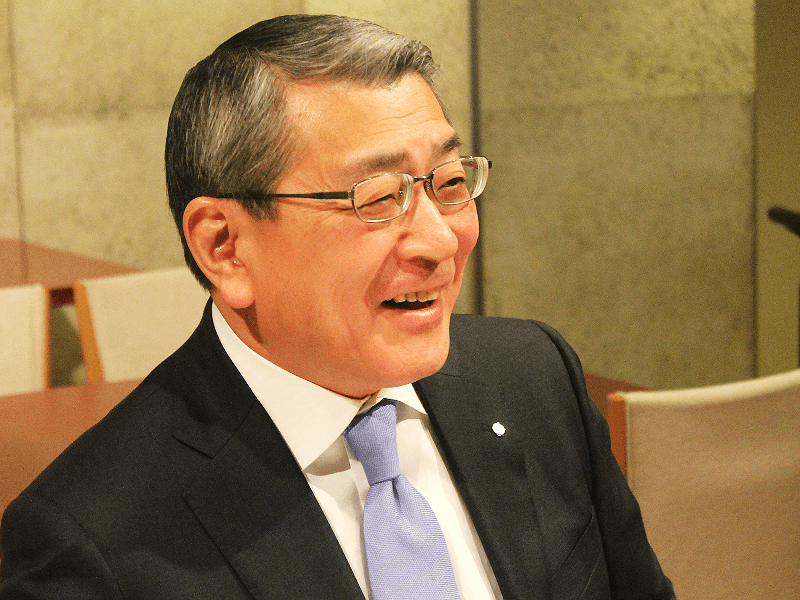
前例がなく、初年度にはたった1蔵のみの参加。本数にして4,000本からスタートした立春朝搾りですが、次年度には出荷本数を2倍以上に増やすなど、着実に規模を拡大してきました。20周年を迎えた2017年は全国34都道府県、40もの酒蔵が参加し、その出荷本数は四合瓶で295,000本にものぼります。
「どんなに増えても、いつも通りやるだけです」と微笑む飯田社長。その表情からは、20年間続けてきた自信と誇りが感じられました。
当日搾りだけではない、地域共感酒としての魅力
"当日搾り"であることが大きな魅力の立春朝搾り。地域イベントとしての側面があるのも特徴です。"地域共感酒"とも呼ばれる本企画には、いくつかの取り組みがあります。
そのひとつがラベル貼りの作業。通常のお酒は蔵人が機械などで貼りますが、「立春朝搾り」だけは特別。立春の早朝に集まった酒販店たちが、1枚1枚心を込めた手作業でラベルを貼って最後の仕上げを行います。

この作業が終わると、参加者全員が酒蔵近くの神社に出向くか、酒蔵に神主さんをお招きして"お祓い"を受けます。日ごろはライバル同士の酒販店たちが一堂に会して、協力しあって作業を行い、厳かなお祓いを受けることで、お酒に対する思い入れと、みんなでこの行事を盛り上げていこうという連帯感が生まれます。
その思いは「立春朝搾り」を買いに来たお客さんにも伝わります。参加した酒販店のなかには「このお酒を買っていただいたお客様から逆に感謝されます。酒屋冥利に尽きますよ」という人も。まさに地域に共感の輪が広がる行事です。
また、作業の合間に、蔵人と酒販店の人たちがいっしょに朝食をとるのも立春朝搾りの恒例行事だそう。ふだんは荷物の受け渡しをするだけで、あまり交流する機会のない酒蔵と酒販店。「顔を合わせてじっくり話す良い機会があるのはうれしい」と、双方からお礼を言われることも多いのだそうです。
これらの仕掛けを作った背景について、飯田社長はこう話します。
「地元に酒蔵があっても、地域との繋がりは意外と薄い場合もあるのです。酒蔵と酒販店もそう。せっかく地域に根差しているのだから、酒蔵と酒販店、地域の人たちを繋ぐきっかけを作りたかったんです」
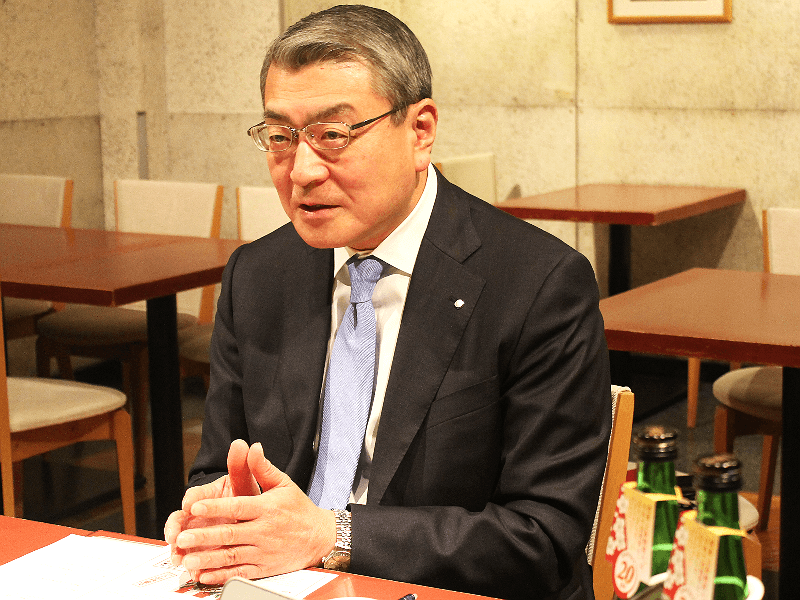
地域に根差した酒蔵、酒蔵の酒を売る酒販店、酒を買って飲む地域の人たち。立春朝搾りは“単なる搾りたての新酒”に留まらず、“地域共感酒”として、ひいては3者が一直線上に繋がる“仕組み”として20年もの間、機能し続けてきたのです。
"日本酒界のプラットホーム"、日本名門酒会の役割
地域と酒販店、そして酒蔵を結ぶ企画を20年以上も続けてきた日本名門酒会。みずから酒を造る酒蔵でも、酒を販売する酒販店でもないとすると、どんな役割を担っているのでしょう。
日本名門酒会を主宰する株式会社岡永は、酒蔵と酒販店を繋ぐ卸売業、いわば問屋という位置づけです。当時は中間流通の存在意義が問われていた時期。「酒蔵と酒販店の間に立ち、ただ商品を流すだけの存在」と揶揄されたこともあったそうです。
そんな最中、あえて立ち上げられた背景には、"中間流通の役割"にまつわる社長のこんな想いがありました。
「中間流通の役割は、価値を広めていくことだと信じてやってきました。酒蔵のようにお酒を造ることも、酒販店のようにお客様にお酒を販売することもしませんが、商品や企画、仕組みを駆使して、酒蔵や酒販店の"点"を"線"で結ぶ使命があると思っているんです。そんな思いから、立春朝搾りの企画が生まれました」
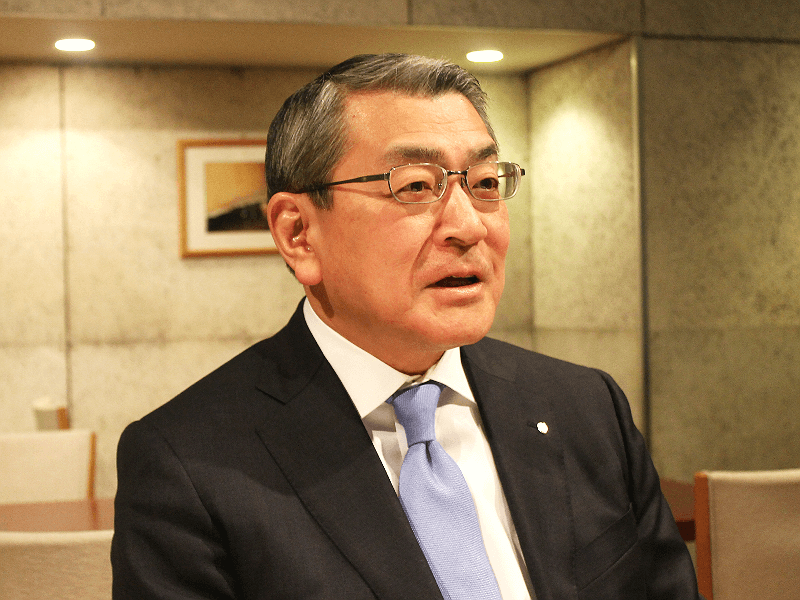
日本名門酒会の役割は、立春朝搾りの推進のみに留まりません。 生酛の研究をはじめとした技術交流や研修、日本名門酒会の市販酒を定期的に審査する「品質管理委員会」など、あらゆる取り組みがなされています。そのすべては日本酒業界全体のレベルの底上げを図るためなのです。
販促の観点から、酒蔵に商品開発のアドバイスをすることもあるようですが、「決して『こういうお酒を造ってください』という押しつけはしない」と、飯田社長は力を込めます。
「酒蔵にはまず、"どういうお酒を造りたいのか"と問いかけて、そのうえで参考としてマーケット情報を渡しています。自分の意志がないとお酒に反映されませんし、日本酒は造り手ありきだと思っているからです」
具体的な提案をしながらも、酒蔵や酒販店に敬意を表し、その主体性を重んじてきた日本名門酒会。風上から風下までを包括する"プラットホーム"のような存在こそ、現代の中間流通に求められている理想形なのかもしれません。
地域の"文化"を目指す「立春朝搾り」
春の訪れを伝える縁起酒、立春朝搾り。
その魅力は、"季節限定"や"搾りたて"といったキャッチーなものだけでなく、地域の人と人とを繋ぐという、日本酒の領域をも超えた役割を担っていました。
飯田社長は未来に向かって、次のように夢を語ります。
「日本酒はブームではなく、文化になってほしいですね。立春朝搾りも『立春だからお酒を買わなきゃ』というくらいに定着してほしいんです 」
日本名門酒会立ち上げから40余年。季節のイベントとして始められ20年目を迎えた「立春朝搾り」は今後も受け継がれ、地域の文化へと変容していくことでしょう。
(取材・文/佐々木ののか)
sponsored by 株式会社岡永





