新潟県新潟市にある石本酒造は、“幻の酒”と呼ばれるほどの人気を誇った銘酒「越乃寒梅」の酒蔵。1970年代の地酒ブームを牽引し、現在もたくさんのファンを抱える酒蔵ですが、近年は約半世紀ぶりの新商品を発売するなど、新しい挑戦にも取り組んでいます。
ひとつの時代を築いた酒蔵が新たな試みを進める中、そこで働く若手社員の方々は、どのような思いで仕事に向き合っているのでしょうか。今回は、石本酒造の20〜30代のメンバー3名に集まっていただき、座談会形式で話を伺いました。
◎座談会に参加していただいた方々
- 小布山力也さん(製造部/29歳/入社10年目)
- 臼井一貴さん(生産本部/35歳/入社4年目)
- 川端麻里さん(営業部/34歳/入社5年目)

生産本部の臼井一貴さん(左)、営業部の川端麻里さん(中央)、製造部の小布山力也さん(右)
「日本酒を造る」を仕事にした理由
—まずは、石本酒造に入社した経緯を教えてください。
小布山力也さん(以下、小布山):短大を卒業してすぐに入社したのですが、きっかけは校内で見かけた求人案内でした。金属加工の技術を身に付ける学校なので、求人のほとんどが機械系の企業だったのですが、酒蔵というところに目を惹かれました。祖父が毎日晩酌するほどの日本酒好きだったので、日本酒がどうやって造られているのか、興味があったんです。
臼井一貴さん(以下、臼井):私は、3年前に石本酒造へ転職しました。大学を卒業した後、関東で自動車の部品を製造する仕事に携わっていたのですが、30歳になる前に地元に帰りたいと思って、仕事を探していたんです。そんな時、ふと立ち寄った移住イベントで、石本酒造の存在を知りました。
川端麻里さん(以下、川端):私は栃木県出身で、大学時代は山形県で暮らし、新潟県へ移住しました。以前は農協で営農指導の仕事をしていたのですが、引っ越しに伴って仕事を続けられなくなり、近所で働き口を探していた時に見つけたのが石本酒造だったんです。当時、子どもがまだ小さかったので、自宅から近いという点がもっとも大きな理由でした。

製造部の小布山力也さん
—入社の決め手は何でしたか。
小布山:実は「越乃寒梅」のことは、あまり知りませんでした。ただ、友人や知人に「どんな仕事をしているのか」と聞かれた時に「日本酒を造っているんだ」って言えたらかっこいいなと思って(笑)。そんな単純な動機でした。
臼井:その気持ち、私もわかります。日本酒は好きで飲んでいましたが、私も酒蔵のことはほとんど知らなくて。薄暗い蔵の中で職人が造っているというイメージだったのですが、見学した時に想像以上に機械化された設備を見て、これなら自分の経験が活かせるかもしれないと思いましたね。
川端:大学のころから日本酒が大好きなんです。前職は農家の年配の方々とお話しすることが多かったのですが、普段は無口な方でも、いっしょに日本酒を飲むと仲良くなれたりして、日本酒の力を実感する経験がたくさんありました。面接を受けたのがちょうど大吟醸酒の仕込み中で、酒蔵全体に良い匂いがしていたことも決め手になったかもしれません(笑)。
—普段はどんな仕事をしていますか。
小布山:原料処理を担当して10年になります。原料処理とは、洗米から浸漬を経て酒米を蒸し上げるまでの工程です。繁忙期は製麹や上槽を手伝うこともありますね。日本酒の仕込みがない夏場は、焼酎や梅酒を造ったり、醸造機械のメンテナンスや掃除をしたりしています。

小布山:普段は8時に始業して、午前は蒸米の作業を行います。米が蒸しあがったらすぐに機械を洗浄して、午後は洗米の作業をすることが多いですね。最後は機械の点検をして、17時に終業します。4日に一度は夜番があるので、その時は会社に泊まることもあります。
臼井:私は醸造設備の担当ですが、普段は瓶詰めのサポートをしていることが多いですね。それ以外の時間は、設備のメンテナンスや掃除にあたっています。勤務時間は小布山さんと同じく8時から17時で、残業はほとんどありません。
川端:取引先からの注文に合わせて瓶詰めのスケジュールを立てる、生産管理のような業務がメインです。他にも、商品ラベルのリニューアルや販促物の作成など、企画や広報のような仕事も担当しているので、“何でも屋”のような立ち位置ですね。
—小布山さんは、石本酒造が主催する酒米研究会にも参加していると聞きました。
小布山:五百万石という酒米を育てている地元の農家さんと石本酒造が取り組んでいる「新潟大江山産酒造好適米研究会」に会社の代表として参加しています。酒米の栽培状況を見回ったり、酒米の勉強会を企画したり、農家さんやJAとのやりとりも担当しています。原料米の栽培に関わるようになって、酒造りの時に米質の状態を適切に把握できるようになりました。
—川端さんの仕事は、一般的な営業職のイメージとは違いますね。
川端:そうかもしれません。そもそも、私が入社するまでは営業担当がいなかったそうで、立ち上がったばかりの部署なんです。最初は手探りで不安でしたが、少しずつ慣れてきて、スムーズに仕事を進められるようになってきました。

営業部の川端麻里さん
—仕事をしていて、どんな時にやりがいを感じますか。
小布山:原料処理は酒造りの最初の工程なので、後の工程に自信を持って酒米を託したいという思いがあります。酒米を吸水させる浸漬の工程では、酒米の状態を目視で確認しているのですが、自分の判断で時間を計って想定どおりの吸水率になった時はうれしいですね。数字として結果が出るので、プレッシャーも大きいのですが(笑)。
川端:私も、入社した当初はプレッシャーを感じていました。最近は、需要予測の精度が少しずつ上がって、余裕を持った製造計画の立案ができるようになりました。コロナ禍による変動の大きい時期を乗り切れたので、自信がつきましたね。あとは、新商品発表会の時にお披露目用のボトルのラベルが濡れてボロボロになってしまったことがあって。念のためにと持参していた予備のラベルでピンチを乗り切った時は、自分を褒めてあげたくなりました。
臼井:ふたりとも、うらやましいです。正直、何かを成し遂げたという実感はまだなくて、これからだと思っています。例えば、瓶詰めラインをもっと効率化したいと考えています。酒質に影響のない範囲で改善できることは、どんどん進めていきたいですね。それが実現した時に、大きなやりがいを感じられるのかもしれません。今は、“将来実現したいこと”を思い描くことが、モチベーションになっています。
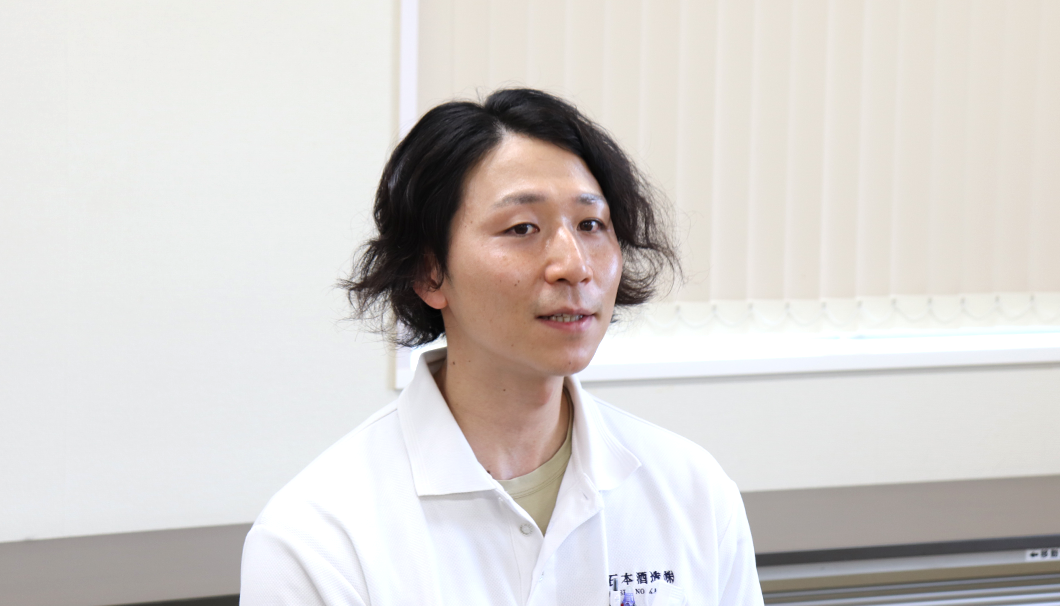
—石本酒造に入社して良かったと思うことは何ですか。
小布山:食に興味がないタイプだったのですが、入社してすぐに杜氏から「酒造りをしているなら、食べ物にも興味を持ちなさい」と言われたのをきっかけに、日本酒と料理をいっしょに味わう楽しさを知りました。今では、食べ歩きが趣味になりましたよ(笑)。石本酒造に入社して、人生が豊かになりましたね。
臼井:こうして落ち着いて仕事ができている現状にまず満足しています。当初の目的は、地元にUターンすることだったので、石本酒造に入社したことで希望を叶えることができました。
川端:子どもたちから「お母さんのお酒があったよ」「先生が『越乃寒梅』が好きだと言ってたよ」と聞くと、素直にうれしいんですよね。子どもたちに誇れる仕事ができていると感じます。あと、石本酒造は育児に寛容だと思います。

小布山:確かにそれは実感しています。2歳になる子どもがいるのですが、生まれた時にきちんと育休を取得できましたし、有給休暇にも理解があります。福利厚生がしっかりしていますよね。
川端:石本社長が、社員をとても大事にしてくれています。毎月のミーティングでは「みんなが楽しく働けるように気を配っていきましょう」というようなことをいつも話してくださって、とにかく優しいんですよ。
臼井:そういう意味でも、Uターンなどの移住を検討している方におすすめできる会社だと感じますね。自分も、より良い雰囲気づくりに貢献していきたいです。
先入観のない若手が、石本酒造を変えていく
—石本酒造のこれからに対して、どんなことを考えていますか。
臼井:日本酒の世界では、手作業のほうが良いという風潮もありますが、私としては思い切って機械化したほうが良いところもあると思っています。品質を落とさずにコストを下げられるのであれば、絶対に取り入れるべき。ただ、一気に変えるわけにはいかないので、少しずつそういう提案をしていきたいですね。
川端:お客様と話していると「石本酒造は変わらずにいてほしい」と言われることもありますが、時代に合わせて変えていく部分も必要だと思います。「越乃寒梅」というブランドに対して、良い意味で先入観のない私たちだからこそできることもあるのではないでしょうか。ちなみに、私は搾りたての生原酒が好きで、そういうお声をいただくこともあります。

小布山:「越乃寒梅」は熟成した酒質を大事にしているので、難しい部分もあるかもしれませんが、実現したらおもしろいと思いました。最近は「灑(さい)」や「浹(あまね)」のように、これまでの「越乃寒梅」とは異なるコンセプトの商品も増えてきています。私が入社した10年前と比べると、新しい挑戦に取り組みやすい雰囲気になってきていると感じています。
臼井:そういう点で言えば、私の仕事は「どういう設備を導入するか」「どういうスケジュールで生産するか」を考えることなので、新しい商品を造りたいと思った時にきちんと対応できるような準備をしていきたいです。
川端:「越乃寒梅」は営業しなくても売れていた時代を経験していますが、私たちの世代では知らない人も多いです。お客様が生活の中で「越乃寒梅」を目にする機会を増やしていきたいですね。

1970年代の地酒ブームを牽引し、新潟県の日本酒を全国区に押し上げた「越乃寒梅」。
しかし、今回の座談会で話を聞いた3名は、当時の盛り上がりを直接知らない若い世代です。だからこそ、良い意味で先入観のない率直な言葉からは、石本酒造の過去ではなく未来を見据えた姿勢が感じられました。
伝統を受け継ぎながらも変化していこうとする石本酒造を牽引していくのは、彼らのような若い力なのかもしれません。
(取材・文:渡部あきこ/編集:SAKETIMES)
Sponsored by 石本酒造株式会社




