「20年の節目の時は、うまく話せなかったんです。震災から25年が経ったいま、ようやく当時のことをわだかまりなく話せるようになった。5年間という時間が、心を少しずつ変えてくれたのかもしれません」
そう感慨深く話すのは、兵庫県の酒蔵・沢の鶴の牧野秀樹さん。震災当時、醸造課の若手社員だった人物です。
沢の鶴は、1995年1月17日に発生した阪神淡路大震災にて被災。7棟あった木造の蔵がすべて倒壊するという甚大な被害を受けました。そんな中、奇跡的に倒壊を免れたタンクから生まれたお酒が、高級日本酒ブランド「SAKE100(サケハンドレッド)」の第4弾商品「現外(げんがい)」です。
タンクに残された酒母から造られた酒は、5年経っても10年経っても、その風味は固く閉ざされたままでした。しかし20年目、眠りについていた酒が変わり始めたのです。

2020年に醸造から25年目を迎えた「現外」。唯一無二のヴィンテージ日本酒として、どのような時間をたどってこの味わいを得たのか。そして、その味わいの奥にある神戸の人々の想いとは。
「SAKE100」を手がける株式会社Clear・代表の生駒が、あらためて「現外」が生まれた根源をたどります。
「恐ろしいほどに、街が静まり返っていた」
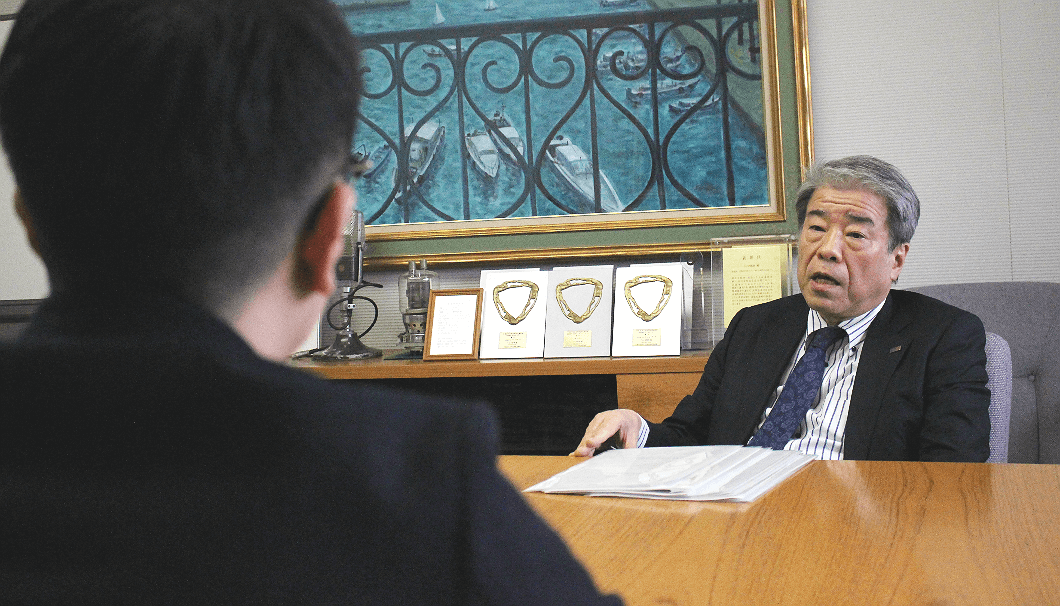
ラジオ関西代表取締役社長・桃田武司さん
震災から25年の節目を迎えた2020年1月。ラジオ関西・代表取締役社長の桃田武司さんにお話をうかがいました。震災当時、神戸市の災害対策本部の取材を担当し、当時の神戸市の状況をよく知る人物です。
生駒龍史(以下、生駒):桃田社長が見た震災は、どういったものでしたか?
桃田社長(以下、桃田):震災の当日、六甲アイランドにある自宅で被災しました。当時、僕は神戸新聞の記者として、市政の報道を担当していたんです。報道に関わる者として、とにかく会社に行かなきゃと。揺れが収まると、夜が明けるのを待って、神戸の街を歩きはじめました。
電車が動かないので、歩いて街へ向かうわけです。六甲アイランドは海に面した埋立地。埋立地と陸をつなぐ橋を渡り終えるころ、対岸の、酒蔵もたくさんある神戸の街全体が視界に入ってきました。
すると、静かなんですよ、街が。恐ろしいほどに静まり返っていた。
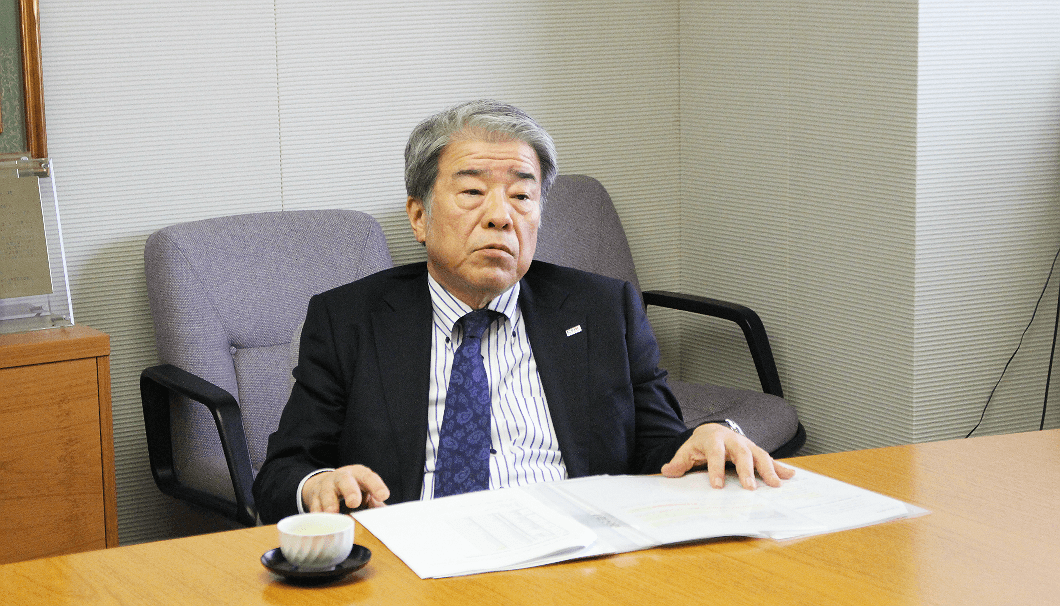
生駒:それは……。
桃田:家々はいびつな形をしていました。1階がないんですよね、押しつぶされてしまって。家の前に立っている人も何人か見かけましたが、茫然自失といった感じで、毛布をかぶってボーッとしているんです。本当に静かでした。
灘区や東灘区は酒蔵も多いエリアですが、どこもかしこも倒壊していました。阪神大震災の被害というと火災のイメージがありますが、東灘区では倒壊がひどかった。今思えば、みんな瓦礫の下で亡くなっていたんだなと。街が異様に静かだったのは、そういう理由だったんです。
やがて、消防車や救急車のサイレンが鳴り響き、空から聞こえるのはヘリコプターの轟音。街は騒然となっていきました。
私は神戸市役所の災害対策本部に泊まり込んで、各地から集約された情報を取りまとめ、発信を続けました。まだ余震だって続いています。そんな中、「六甲アイランドの対岸にあるガスタンクが爆発するかもしれないから、避難が必要」という知らせが流れて。
生駒:ご家族はご自宅にいらっしゃるんですよね。
桃田:ええ。妻と子どもを置いてきた街が、市役所にある私のデスクの窓から見えるんですよ。不安と葛藤で、あの時は本当にきつかった。
生駒:報道の第一線で震災を見ることは、精神的にも大きな負荷がかかりますよね。
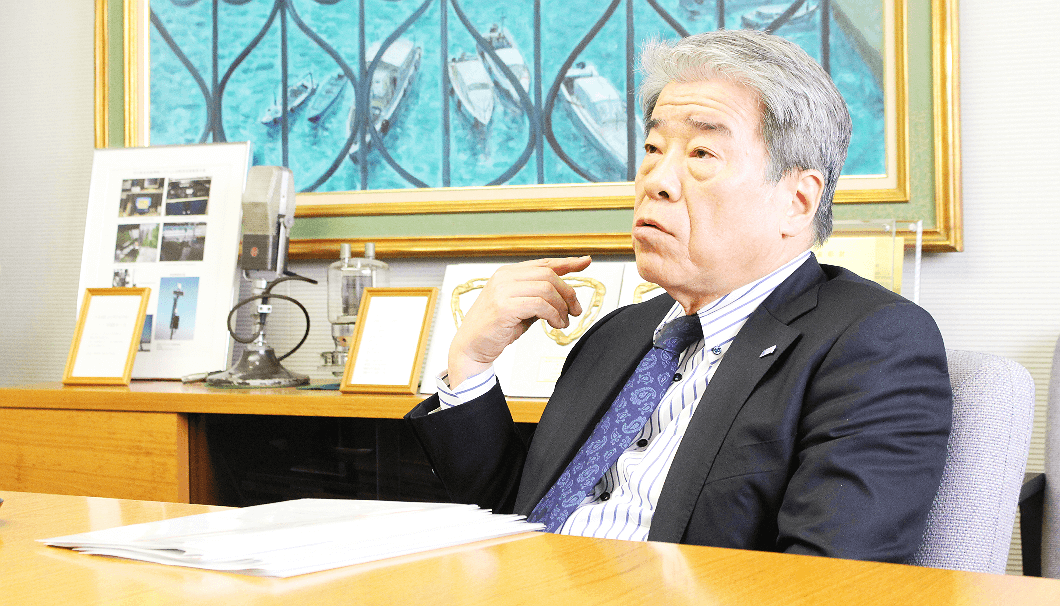
桃田:みんな、涙もろくなっていましたね。でも僕は「いまは泣いている場合じゃない」と言い聞かせて、感情を無理やり封じ込めていたんです。
うん、それでかな......。きちんと泣いていなかったから、後年もその感情がしこりみたいに残ったんですよ。これがなかなかほぐれない。長い時間をかけて、ようやく解消されました。
桃田:全壊家屋104,004棟、被害総額は10兆円規模......。数字は調べればいくらでも出てきますけど、その凄まじさはなかなか実感として湧かないでしょうね。慣れ親しんだ、神戸の街そのものが壊れてしまった。
神様から贈られた、ひとつの"ご褒美"
生駒:心のわだかまりを長い時間をかけて解消したとのことですが、桃田社長が「復興した」と感じたのは、どんなタイミングでしたか?

桃田:この25年で産業構造も大きく変わりました。ほかの都市は順調に発展を遂げてきましたが、神戸の街はマイナスからのスタートです。港も工業地帯も昔ほどの賑わいはないし、神戸を離れてしまった企業も多い。大型のレジャー施設建設の計画も白紙になりました。
神戸の玄関口の三宮は時間がストップしたままだった。やっと動き始めたばかりです。立ち直ったと感じたことはないかもしれません。
でも、そんななかでも生まれてくるものはある。この「現外」はまさにそうですね。
生駒:「現外」は、醪の前段階である酒母の状態で造らざるを得なかった、未熟な酒です。それを蔵の人たちがていねいに守ってきた。そして、20年もの熟成期間を経て、味わいに変化が出てきました。

桃田:なにも知らない人が飲んだら、日本酒とは思わないかもしれませんね。甘みや苦味が複雑に絡んでいるのに、意外と飲み口はさらりとしている。本当においしいお酒です。
生駒:通常、日本酒は醪を搾って造られますが、「現外」は異なるプロセスで造られています。それを熟成させたからか、複雑で重厚感のある香りにもかかわらず、味わいはフレッシュ。このようなお酒は、ほかにありません。
桃田:よくぞ、この味わいになるまで残してきてくれました。未曾有の震災の中を生き抜いてきたことに対する、神様からのひとつのご褒美かもしれません。
7棟の木造蔵が全壊した"あの日"
ラジオ関西の桃田さんに続いてお話をうかがったのは、被災した蔵の復興に尽力した沢の鶴 製造部 次長の今野浩之さんと課長の牧野秀樹さん。沢の鶴は、「現外」を造り熟成させてきた、兵庫県の灘五郷で300年以上の歴史をもつ酒造メーカーです。
生駒:震災が起こったとき、おふたりは蔵にいらっしゃったんですか?

(左から)沢の鶴 製造部・次長の今野さん、課長の牧野さん、株式会社Clear・代表の生駒
牧野課長(以下、牧野):そうですね。当時は、僕も今野も入社して2、3年目の若手だったので、会社の敷地内にあった社員寮にいました。あの日は祝日明けの火曜日で、品評会用の大吟醸酒を仕込む日だったかな。前日に精米を終えて、醪の準備も終えていました。
今野次長(以下、今野):僕は地震が来たとき、「あ、寝坊した」と思ったんです。5時半から作業が始まるのを寝過ごしてしまって。ものすごい揺れを感じました。
牧野:「地震だ!」とは思いましたが、まだ真っ暗だったので、なにがなんだかわからない状態だったんです。寮生たちの無事を確認して、明るくなるのを待ちました。
生駒:沢の鶴さんは、当時7棟あった木造の蔵のすべてが全壊してしまったんですよね。その時の心境は、どういったものだったのでしょうか。

牧野:愕然としましたね。大変なことになってしまったと。ただ、今野は普賢岳や阿蘇山の噴火を間近で見た経験があったんです。そのおかげか、すぐに保険の手続きをするために被災状況の記録撮影をはじめていました。
生駒:その状況で、よく迅速な動きができましたね。
今野:若くて独身で、身ひとつあればなんとかなるという体力があったからでしょうね。「大変なことが起こった、ただなにか行動しないと」という思いで。

生駒:甚大な被害から、どのような形で前に進み始めたのでしょうか。
牧野:片付けを始めたのは本震の翌々日くらいからですね。でも、電柱が倒れていて、電気も通らない。再開には時間がかかると感じました。

ブロック塀の下にあるコンクリートのぶんだけ、地面が隆起・陥没して高さが変わってしまったのだそう。
今野:不幸中の幸いではあるのですが、蔵に米と水はあったんですよね。濁ってしまった地下水をきれいになるまで何度も汲んで、捨てなきゃいけない酒でお米を炊いて。廃材を燃やして、お風呂を沸かしたりもしました。
生駒:大きな不幸の中であっても、たくましいですね。
牧野:「若かったから」が大きいでしょうね。当時の社長(現会長)は「これからどうしていこう」と途方に暮れていました。その絶望感は計り知れません。僕たちは他社に比べて蔵で働く社員が多くいて、なおかつその社員も期間雇用の蔵人さんたちといっしょに造りにも参加していたので、酒造りを再開しやすかった。蔵人集めや蔵の再建がうまくいかず、廃業した酒蔵は多かったようです。
「不確かな未来に懸けてみようとした」
生駒:復興と並走しての造りの再開は、並大抵のことではなかったでしょう。もともと「現外」は、タンクに残った酒母から造った、未熟な酒がスタートです。商品にはできなかったものを、よくここまで残すことができましたね。
牧野:貯蔵タンクを空にするためにも、本当はなんとかして市場に出したかったんです。きちんと造られたお酒に数%ずつブレンドしていって、商品化するという方法もあった。でも「変なものは出しちゃいけない」という思いもあって......。
今野:沢の鶴の技術者には変わり者が多くて、造ったはいいけど社風に合わない味になったお酒や、偶然の産物でできあがったものを「なにか起こるかもしれない」と、アーカイブしていく気風があるんです。

牧野:古酒については40年ほど前から研究していました。当時、純米酒で古酒を造るというアイデアはまだありませんでしたが、沢の鶴には積み重ねてきた知識があった。ひとまず寝かせておいて、未来に懸けてみようとしたんです。
生駒:社風や蓄積された知識があってこそ、「現外」は生まれたんですね。
牧野:寝かせてから5年や10年では、まだ"赤ん坊"の味でしたが、20年が経ってから急に味わいが変わってきました。それから5年が経ち、さらに味が熟成されてきたと感じます。
今野:ただ、これから30年、40年で味がどう変化するのかはわからない。熟成期間が長ければおいしくなるとは限らないので、商品としてあと何年出荷できるのか。それも未知数です。
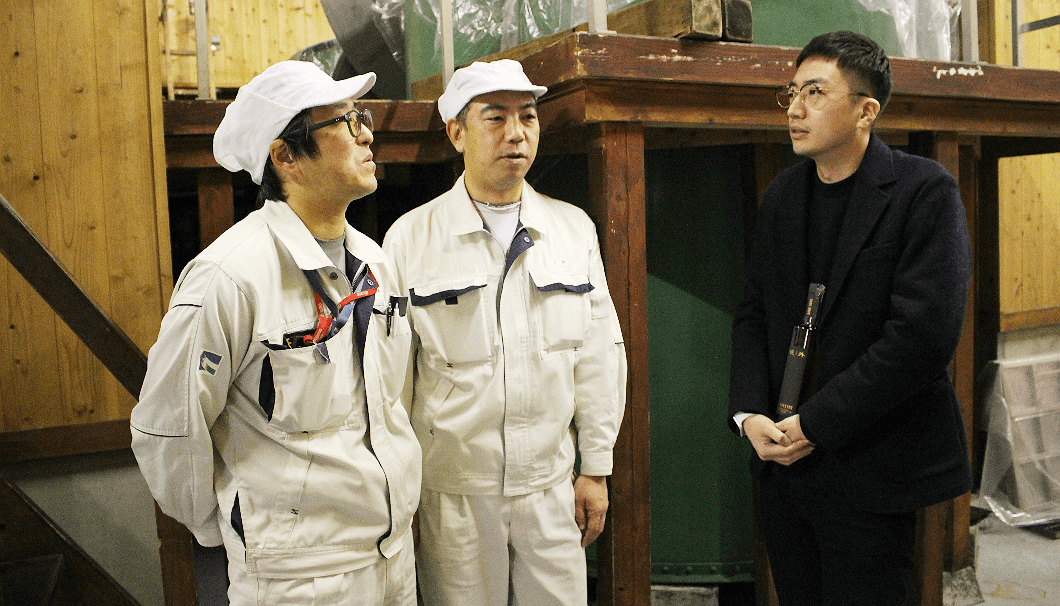
生駒:おふたりが「震災がひと区切りついたな」と感じたタイミングは、いつごろだったのでしょう。
牧野:そうですね......10年くらい経ったころでしょうか。
今野:僕は20年の節目までずっと、毎年1月17日になると線香をあげていました。自分が撮った震災当時の写真も見られませんでしたね。当時を思い出してしまうので。
牧野:20年目にも、こうした震災関連のインタビューを受ける機会がありました。ただ、あの時は今ほどうまく話せなかったですね。まだ怖ろしさや生々しさがあった。25年が経って、ようやくわだかまりのようなものは消えました。
生駒:25年......あまりにも長い時間がかかったんですね。
牧野:震災を経験して、いろんな感情が生まれました。今は勉強になったと感じます。蔵が味わった戦後最大の災害を、後輩に伝えていくひとりになれましたから。
「現外」は"人の意志"から生まれた酒
前例のない大震災の中、生半可ではなかった手探りでの復興。「立ち直ったと感じることはないかもしれない」と遠くを見て語った桃田社長の瞳が、事態の大きさを物語っています。

「20年目は言葉に詰まることもあった。25年目で、ようやく話せるようになった」と話す沢の鶴のおふたり。その姿は、心を閉ざし続けてきた未熟な酒が20年目でようやく変化し、25年の年月を経て、奥深い熟成香と旨味が絡み合う酒となった歩みと重なります。まるで、造り手の心が解きほぐされていくのを、じっくりと待っていたかのよう。
このお酒が持つ価値について沢の鶴から相談を受けた生駒は、ストーリーと常識を覆すほどに複雑で奥深い味わいに衝撃を受け、「SAKE100」での取り扱いを打診。「現在の理(ことわり)の外にある唯一無二の日本酒」という意味を込めて「現外」という名前を付け、販売を開始しました。
この酒が今ここにあるのは、「せっかくだから搾ろう」「捨てないでおこう」「味が変わるまで様子をみよう」......現在までつなげようとしてきた、紛れもない"人の意志"があったからこそ。
「現外」のアンバー色の液面から立ち上る香りは、カラメルのような甘味、ビターチョコレートのような苦味、そしてアーモンドのようなロースト感にスパイシーな印象がアクセント。複雑でいて芳醇な香りです。口にふくむと、甘味・酸味・苦味・旨味が一体となった円熟味を帯びたまろやかさと同時に透明感も感じ、深く長い余韻が残ります。
奇跡に近い「現外」の味わいは、沢の鶴の蔵人たちに秘められた、酒造りへの強い意志が介在していた証ともいえるでしょう。

震災から25年を迎えた2020年1月17日、5時46分。神戸市の東遊園地には今年もたくさんの灯籠が灯され、鎮魂への想いがこだましていました。
多くの被害を生んだ震災を前向きに捉えることはできません。しかしそれでも、苦境の中でも人はなにかを生み出すことができる。そう感じることができた取材でした。
(取材・文/平山靖子)
この記事を読んだ人はこちらの記事も読んでいます
- 創業300年の老舗酒蔵が見つめるのは“次の100年”─ 沢の鶴を牽引する新リーダー・西村隆社長が考える、みずからの使命
- 高級日本酒ブランド「SAKE100」の1995ヴィンテージ日本酒『現外2020』が1/17(金)に瓶詰めを行い本発売開始
- 阪神大震災を乗り越え誕生した奇跡の24年熟成酒のポテンシャル ─ SAKE100第4弾商品『現外 -gengai-』リリースイベントレポート
- “100年誇れる1本”で日本酒の高価格市場を開拓する「SAKE100(サケハンドレッド)」の挑戦【Clear Inc.代表取締役CEO・生駒龍史インタビュー】
- 最高級日本酒ブランド「SAKE100」が挑戦する日本酒業界の課題─ 必要なのは『リスクを背負える新しいプレイヤー』

