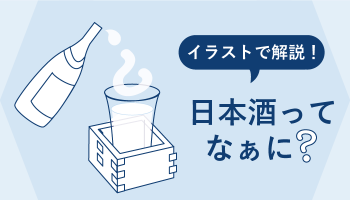「伯楽星」や「愛宕の松(あたごのまつ)」といった日本酒で知られる宮城県の新澤醸造店が、国内外のさまざまな日本酒コンテストで快進撃を続けています。
世界的な影響力をもつといわれるワインの品評会「International Wine Challenge(インターナショナル・ワイン・チャレンジ/以下「IWC」)」のSAKE部門では、2025年は、各審査カテゴリーのトップにあたる「トロフィー」を2点が受賞。
さらに、出品酒のすべてが高評価を得た酒蔵に与えられる「Sake Brewer of the Year(サケ・ブリュワー・オブ・ザ・イヤー)」を2022年から2025年まで4年連続で受賞するという快挙を成し遂げました。

また、国内外の有力な日本酒コンテストでの実績を点数化して酒蔵を格付けする「世界酒蔵ランキング」では、2022年から2024年まで3年連続で世界1位を獲得しています。
新澤醸造店が、コンテストでこれほどの圧倒的な実績を築いているのは、なぜなのでしょうか。酒蔵を訪れ、その酒造りについてお話をうかがいました。
「おいしい」を科学する論理的なアプローチ

1873年(明治6年)に宮城県大崎市(旧 三本木町)で創業した新澤醸造店。地元を中心に愛されてきた「愛宕の松」に加え、2002年に「究極の食中酒」をコンセプトとした「伯楽星」を生み出し、どちらの銘柄も高く評価され続けています。
国内外の日本酒コンテストにおける圧倒的な実績だけでなく、精米歩合0.85%という究極の精米を実現した「零響 -Absolute 0-」を発売するなど、日本酒業界の最前線を走り続ける酒蔵です。

新澤醸造店の新しい甑。左が麹米用、右が掛米用。
この夏から、麹造りをより精密に管理するために、これまで1台のみだった甑(こしき/米を蒸す機械)を、麹米用と掛米用に分けて2台としました。
「麹米と掛米を分けて蒸すことで、それぞれの水分量を最適化するのが目的です。蒸米の出来をより細かくコントロールすることで、後口のキレをさらに磨きつつ、その一方で味が軽くなりすぎないように、麹造りを工夫して強いコシを出していきます」
そう説明してくれたのは、代表取締役の新澤巖夫(にいざわ・いわお)さん。新澤醸造店では、常に完成形から逆算し、理想のおいしさとする目標の数値へ近づけていくための酒造りを日々追求し続けています。

新澤醸造店 代表取締役 新澤巖夫さん
酒質の分析にも、最新の機器を活用。従来の製品よりも分析のスピードが早く、蔵人が出勤してすぐにセットすることで、その日のうちに分析結果を踏まえた対策を打てる体制が整っています。また、日本酒コンテストの上位入賞酒はすべて、酒質をデータ化してまとめ、毎年の傾向を分析しています。
おいしい日本酒を造るために新澤醸造店がもっとも大事にしているのが、蔵人のテイスティング能力を徹底的に磨くこと。蔵人全員で約100種類の日本酒をブラインドテイスティングする「サーキット」や、飲んだ銘柄を当てる「マッチング」などのトレーニングを定期的に行っています。
また、どんな環境でもおいしいと感じてもらえるように、3パターンの室温でテイスティングし、自社の日本酒の特徴を身体で理解しています。
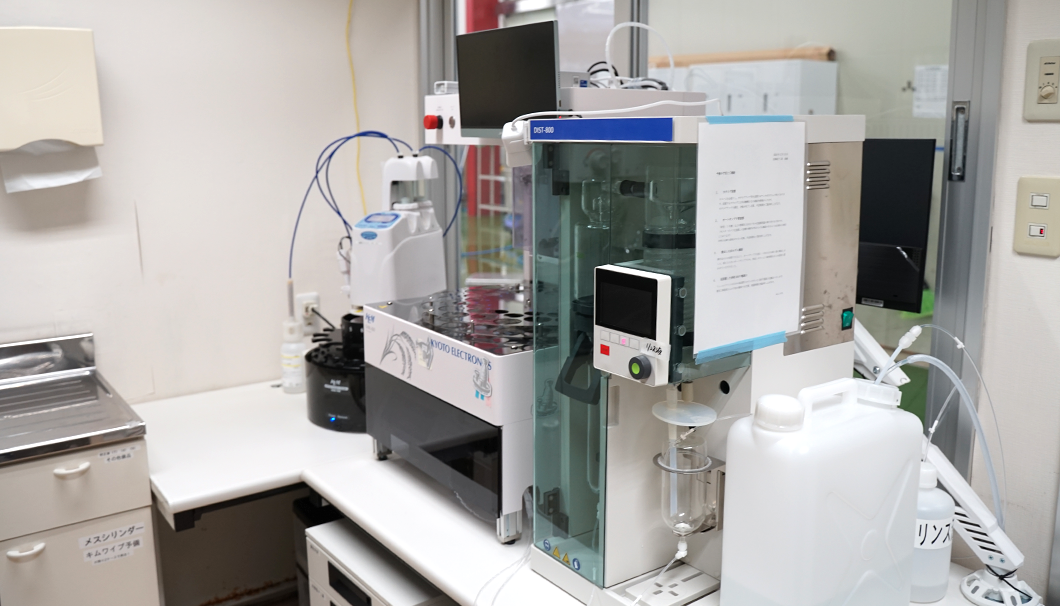
新澤醸造店の分析機器
一方で、より良い酒造りに必要なものを考える時間を確保したいという思いから、商品の箱詰め作業はロボットを導入して自動化するなど、単なる“作業”をなるべく減らし、効率化を進める高い意識が随所にみられます。
「どの工程にも、改善したいところがたくさんあります。酒造りは自動車のチューニングに似ていて、どこかをひとつ直すと全体のバランスが崩れてしまう。でも、ゼロからやり直すことを恐れずに改良を重ねれば、より精度の高い、理想的な酒造りに近づけることができるんです」(新澤さん)

IWCは、評価基準が明確なコンテスト
2025年のIWCでは、なんと合計19点の出品酒が金賞を獲得。各審査カテゴリー(全10部門)のトップに与えられるトロフィーの称号は、本醸造酒部門で「愛宕の松 県内本醸造」が、熟成酒部門で「超特撰 純米大吟醸 残響2018」が受賞しました。
さらに、トロフィーの次点に与えられるリージョナル・トロフィーが3点、商品の価格や生産量をもとに優れたコストパフォーマンスの出品酒に与えられる賞「Great Value Sake(グレート・バリュー・サケ)」も獲得しています。
加えて、エントリーした複数の出品酒すべてが高い評価を得た酒蔵に贈られる「Sake Brewer of the year(サケ・ブリュワー・オブ・ザ・イヤー)」も受賞し、こちらは2022年から数えて4年連続受賞という快挙です。

- 【本醸造酒トロフィー】「愛宕の松 県内本醸造」(右から2番目)
- 【熟成酒トロフィー】「超特撰 純米大吟醸 残響2018」(中央)
- 【宮城・純米大吟醸トロフィー】「NIIZAWA KIZASHI 2021」(左から2番目)
- 【宮城・本醸造酒トロフィー】「愛宕の松 別仕込本醸造」(最右)※グレート・バリュー・サケも受賞
- 【宮城・熟成酒トロフィー】「NIIZAWA 2018」(最左)
実は、2020年ごろまでは、コンテストに出品する習慣はなかったのだとか。コロナ禍による飲食店の営業制限などで売上が停滞した時期に、従業員のモチベーションを上げるために、積極的にエントリーするようになったといいます。
海外の日本酒コンテストのなかでも、「IWCは審査員のレベルが抜群に高い」と評価する新澤さん。
「ブラインドテイスティングの審査で、毎年のように同じ酒蔵が上位入賞することが多いのは、審査基準がブレていないから。しっかりと実力のある酒蔵が評価されているコンテストだと感じます」(新澤さん)

新澤さんによると、コロナ禍の前後に市販酒を分析して比較した結果、全体的に甘味が強くなってきていることがわかりました。
新澤醸造店は、料理に寄り添う「究極の食中酒」を目指し、甘味を抑えたお酒を造っていますが、このときは時代の流れに追随すべきか悩んだそうです。
「そんななか、IWCのような審査基準が明確なコンテストに出品して評価を受けることで、『自分たちの方向性は間違っていない』と確認することができました。これは大きな自信につながりましたね」(新澤さん)

新澤醸造店の最高峰の商品「零響 -Crystal 0-」
さらに、コンテストでの受賞を通して何よりも変化したのは、日本酒業界の外からの反応です。
「人によって『おいしい』の基準は違います。ただ、コンテストやランキングという客観的な評価軸があると、特に業界外の方にとっては説得力が増すということがわかりました。
IWCは特に権威性が高く、受賞した『伯楽星』や『愛宕の松』だけでなく、弊社の最高峰の商品『零響 -Crystal 0-』の注文が入ったときは『受賞酒だけでなく、他の商品も注目してもらえるんだ』と、影響力の強さを実感しました」(新澤さん)
甘味に頼らず、食事を引き立てる味わいを
新澤醸造店のハイレベルな酒造りを現場で率いるのが、杜氏の渡部七海(わたなべ・ななみ)さんです。
入社3年目の2018年、22歳という若さで当時の全国最年少杜氏となった渡部さんは、さまざまなコンテストへ出品するようになったころを、次のように振り返ります。

新澤醸造店の杜氏 渡部七海さん
「コロナ禍で出荷が止まったとき、新澤社長が『この状況はいつか落ち着くから、そのときに自信をもって商品を届けられるように品質を上げていこう』と言ってくださったのが心に残っています。
コンテストを通して、順位や賞という見える形で結果が出たことで、従業員のみんなが『いまのやり方が間違っているわけじゃないんだ』と確認することができ、モチベーションを維持することができました」(渡部さん)

新澤醸造店では、年に一度、全国の取引先を回り、飲み頃を過ぎた商品を回収・交換する「フレッシュ・ローテーション」を実施しています。
その取り組みのなかで、同じ規格の商品でも、地域の気候や口にするタイミングによって、香りや味わいの感じ方が少しずつ異なることを実感したのだとか。
それ以来、すべてのお客さんに同じおいしさを届けるために、取引先ごとに数値をわずかに変えて出荷する方針を取っています。
コンテストに関しても同様に、開催地までの輸送方法や、出品から審査までの期間を考慮し、審査のタイミングでもっとも良い状態になるようにタンクを選別。
その一方で、「造りの方針をコンテストに合わせることはありません」と渡部さん。あくまでも目指すのは、新澤醸造店が誇る「究極の食中酒」としての味わいです。

「『究極の食中酒』とは、どんな料理にも合うお酒のこと。具体的には、糖分を少なくして、甘味に頼ることなく食事を引き立てる味わいに設計しています。
しかし、やりすぎると『味が痩せている』と思われてしまうので、ソフトな口当たりになるように工夫してきました。いまは、よりスレンダーな味わいにするために試行錯誤しています」(渡部さん)

渡部さん曰く、杜氏の役割は「全員が働きやすい環境をつくること」と「酒造りの方向性を決めること」だそう。
「細かいことでいえば、台車が壊れていないかをチェックして、壊れていればすぐに直すように指示するのも、杜氏の仕事です。どんなに小さなことでも、現場の課題をひとつずつ改善していくことで、各工程を効率化し、みんなが課題を共有しやすい環境をつくりたいと思っています」(渡部さん)

「酒造りの方向性の指示については、まだまだ課題もあります。私は『もう少し軽く』というような感覚的な指示をしてしまいがちなんですが、『1割軽く』というように、具体的な数値で明確に伝えることを心がけています。
ただ、すべてを数値で指示してしまうと、スタッフの工夫の余地が少なくなってしまう可能性もあるのが難しいところです。ひとりひとりとたくさんコミュニケーションをとりながら、『どうしたらいいと思う?』と聞いて、なるべく自分で考えてもらうようにしています」(渡部さん)
「究極の食中酒」を求めて次のステージへ
新たな設備を導入した酒造りを前に「最適なやり方をゼロから考える必要があるんですが、それが楽しいですね」と微笑んだ渡部さん。
「最近は酒米の価格が上がっているので、商品の原価や製造の効率化も強く意識するようになりました。昨シーズンは、製造の現場を離れて人事や統括の仕事に関わったのですが、酒蔵の経営を数字の面からも考えられるようになったのは大きな変化です」(渡部さん)

さまざまな日本酒コンテストで結果を出しながらも、「現在の品質にまだ満足していない」と新澤さん。目指しているのは「軽快でありながら薄っぺらい印象はなく、美しいと感じる日本酒」だと話します。
「数値で説明できる部分の品質はクリアしてきているので、これからは、その先にある複雑で抽象的な領域に挑みたいと考えています。『今年は米の質が変わったから仕方ない』なんて言い訳はしません。課題に対して技を増やしていきながら、磨き抜かれた唯一無二の美しさを表現したいですね」(新澤さん)

新澤醸造店が、4年連続の「Sake Brewer of the Year」という快挙を達成した背景には、新澤社長と渡部杜氏が中心となり、技術を磨き続ける日進月歩の努力がありました。
またひとつ、日本酒コンテストにおける圧倒的な実績を更新した新澤醸造店。その日本酒は、これからもますますおいしく進化し続けるのでしょう。
(取材・文:Saki Kimura/編集:SAKETIMES)
今年の上位入賞酒を楽しめるイベントが10月に開催!
「IWC 2025」のSAKE部門で選ばれた上位入賞酒を楽しめる日本酒イベント「プレミアム日本酒試飲会」が、10月18日(土)に開催されることになりました。このイベントは、今年で通算12回目の開催となります。
当日は、全国の23蔵から26点の銘酒が集結します。この機会に、世界が評価した最高峰の日本酒を飲み比べてみてください。
◎イベント概要
- 名称:プレミアム日本酒試飲会
- 日時:2025年10月18日(土)
・日本酒トークセッション 12:45〜14:00
・第1部 14:00〜15:30
・第2部 16:30〜18:00
※各部入れ替え制。開始時間の30分前から受付。 - 会場:YUITO 日本橋室町野村ビル 野村コンファレンスプラザ日本橋 6階
※受付は5階。 - チケット種類(料金)
・日本酒トークセッション&第1部(4,800円)
・第1部のみ(4,800円)
・第2部のみ(4,800円)
※前売券のみの販売となります。当日券の販売の予定はありません。 - チケット販売ページ
・e+(イープラス)
※定員に達し次第、締切となります。 - 注意事項:
・20歳未満の方はご参加いただけません。
・車でのご来場はご遠慮ください。
・体調のすぐれない方のご参加はご遠慮ください。
・出展銘柄など、イベントの内容は変更になる場合がございます。
・「IWC 2025」のすべてのトロフィー受賞酒が提供されるわけではありません。
・新型コロナウィルスなどの感染状況によっては、イベントを急遽または予告なく中止・変更させていただく場合があります。 - 主催:野村不動産株式会社
- お問い合わせ:03-3277-8200(YUITO運営事務局)
Sponsored by 野村不動産株式会社