長野県の南部、天竜川に沿って南北に伸びる盆地「伊那谷(いなだに)」のほぼ中央に位置する中川村。NPO法人「日本で最も美しい村」連合に加盟しているこの村の風景で特徴的なのは、川の侵食によってつくられた河岸段丘です。その段丘には棚田がつくられ、米作りが盛んに行われてきました。

この地で1907年から酒造りを行ってきたのが、「今錦」を醸す米澤酒造です。
後継者の不在や設備の老朽化などといった問題から、一時は廃業の危機に立たされますが、2014年、同じく長野県の企業である寒天メーカー・伊那食品工業のグループ会社となって、新たなスタートを切りました。
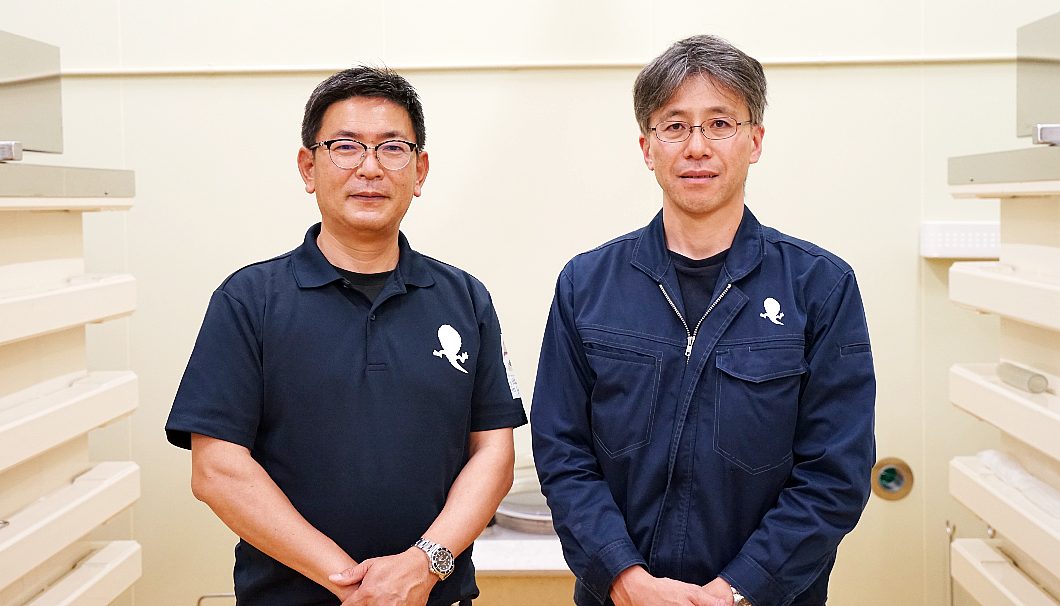
米澤酒造 専務取締役・松下一成さん(写真左)と杜氏・坂口竣弥さん
「地域の文化として酒蔵を残したい」という想いで事業継承を行った伊那食品工業による新体制となり、米澤酒造の酒造りにはどのような変化が起きたのでしょうか。
変わったこと、変わらなかったこと、そして、あえて変えなかったことについて、米澤酒造の専務取締役・松下一成さんと杜氏・坂口竣弥さんにお話をうかがいました。
酒造りの設備を、ほぼ一新

米澤酒造を訪れると、真新しい建物が目を引きます。売店や応接室をはじめ、蔵の建物も新築です。新しいのは建物ばかりではなく、酒蔵の中にある設備も同じ。なんと、総額でおよそ8億円をかけ、設備のほとんどを一新しました。

事業継承を機に、伊那食品工業から米澤酒造に出向した松下さんは、「当初はここまで大がかりに入れ替えるとは思っていませんでした」と話します。
いくつかの酒蔵で蔵人として働いてきた経験を持つ坂口さんは、事業継承直後の米澤酒造の印象を次のように振り返ります。
「これまでに見たことがないくらい古い蔵で、老朽化が進んでいましたね。排水が上手くいかないから、蔵人みんなでバケツリレーをするなんてこともありました」(坂口さん)
古い設備だからといって酒造りができないわけではありませんが、衛生面が心配だったこともあり、数年をかけて設備の入れ替えを行いました。
1年目にまず導入したのは、寒天製造でもなじみのあった貯蔵庫や冷蔵庫です。温度管理を徹底することで、お酒の味わいが良い方向へと変わったことを実感したといいます。

続いて、2年目には麹室を新設。「まだまだ日本酒の勉強中でしたから、酒造りの根幹である麹室に手を入れるのは勇気が必要でした」と、松下さんは当時の心境を振り返ります。
麹室には、新たに「ロードセル」と呼ばれる電子重量計を導入。これによって、米の重さと水分含量を正確に管理できるようになりました。
「個人的な印象ですが、酒の味わいに一番影響を与えるのは麹ではないかと思っています。ですから、ロードセルの導入は絶対に必要でした」(坂口さん)
3年目にはタンク室や造り蔵を新たに建設し、蔵全体がほぼ一新されました。
伊那食品工業との関わりから生まれた変化

家庭用寒天製品「かんてんぱぱ」シリーズを展開し、寒天の国内シェアで約80%を誇る伊那食品工業は、衛生管理を徹底してきた会社です。新たに生まれ変わった米澤酒造の蔵には、伊那食品工業ならではのノウハウが取り入れられています。
たとえば、日本酒の仕込みタンクは専用の台を使い、それぞれのタンクが同じ高さになるように底上げをしています。この台は、伊那食品工業が独自に製作したものです。
実は、寒天メーカーは国内に数えるほどしかなく、寒天の製造に使用する専門機器はかなり限られます。そのため、伊那食品工業では既存の機器を自社でカスタマイズして使うのが常でした。そうして培ってきた独自の工夫のスキルが、米澤酒造でも活かされているのです。

「タンクの下にはゴミが溜まったり、蜘蛛の巣が張ったりしがちなのですが、これだけ底上げされていると掃除がしやすいんです。衛生的で、とても気に入っています」(坂口さん)
なるべく作業の動線が重ならないよう、設備のレイアウトも調整。衛生的な環境を保ちつつ、効率的に仕事を進められるように工夫を重ねました。
また、設備面だけでなく、人の流れにも変化が。機器の担当、研究の担当など、伊那食品工業のさまざまな担当者が米澤酒造を訪れるようになり、新たな交流が生まれています。
「伊那食品工業の方とは、仕事の話はもちろん、趣味の話をするときもあります。蔵人は閉鎖的になりがちなので、いろいろな人とお会いできるのは単純にうれしいですし、刺激になりますね」と、坂口さんは事業継承で起きた変化を前向きに話してくれました。
引き継がれる酒蔵の伝統「槽搾り」
一方で、事業継承を経た現在でも、変わっていないこともあるようです。
そのひとつが、米澤酒造の酒造りの大きな特徴である「槽搾り(ふなしぼり)」。細長い酒槽に醪を入れた酒袋を何層にも重ねて、上からゆっくりと圧力をかけて日本酒を搾る方法です。この方法は、現在も変わらずに引き継がれています。

「槽搾りは、米澤酒造の"売り"といえるもの。今では全量槽搾りをしている酒蔵は珍しくなりましたし、酒蔵を継承する以上、わたしたちが文化として残すべきものだと考えています。
ただし、文化を残すといっても、私たちは博物館ではありません。事業である以上、想いだけでは足りません。酒造りを持続させること、発展させることを考える必要があります。槽搾りを継承することを決めたのは、製法的にもメリットがあったからです」(松下さん)

「槽搾り」を続ける意味について、杜氏の坂口さんは次のように語ります。
「槽搾りは、意外と効率が良いんですよ。たしかに、一般的にはヤブタ式のほうが効率に優れているのですが、うちくらいの規模だと、洗浄などの時間も考えると、かえって非効率になってしまう場合もあります。槽搾りは構造が単純なので、洗浄の手間も少なく、衛生管理がしやすいんです。
また、無理な圧力をかけずに搾ることができるので、雑味も出にくい。やわらかく、澄み切った味わいを表現するためにも、槽搾りは欠かせない製法だと思っています」
それまで長年使われてきた木製の槽は2021年に引退し、より衛生的で使い勝手の良いステンレス製の槽に変わりましたが、米澤酒造の伝統である「槽搾り」は、文化としての価値に加え、製造効率や目指す酒質も踏まえて、変わらずに継承されました。
日本酒の味わいに磨きをかける

設備を一新し、一見すると大きく変わったように思える米澤酒造。しかし、酒の味わいの輪郭となる部分は変えずに、酒質をさらに向上させています。
「基本の配合は、ほとんど変えていません。設備を新しくして、今までのやり方をブラッシュアップしたというイメージでしょうか。新しくなった米澤酒造の日本酒について、昔から飲んでくださっているお客様の声で印象的だったのが、『洗練された』『雑味がなくなった』というものです。かつての米澤酒造の味わいが"原石"だとしたら、私たちはそれに磨きをかけて、輝きが現れてきたような気がします」(松下さん)

また、地域との関わり合いも、変わっていないもののひとつです。
米澤酒造は、中川村の棚田で地域の人たちと一緒に米を育て、その米で日本酒を仕込むなど、地域との関わりを長く続けてきました。伊那食品工業も、敷地の間を通る広域農道に自己負担で歩道橋を設置したり、会社周辺の清掃を定期的に行うなど、地域との関わり合いを大切にする文化があります。
「地域の方と協力して米づくりを行っているからこそ、米を見れば『今日はAさんの田んぼの米だ』と、すぐに生産者の方の名前が浮かびます。同じ中川村でも、生産者の方によって米の扱い方がまったく違うんです。『Bさんの米は少し長めに吸水させようか』など、データが蓄積されていくので、年々、より深く米と向き合うことができていますよ」(坂口さん)

2022年からは、伊那食品工業グループが中川村の棚田の維持管理を引き継ぎました。今後は伊那食品工業の社員とともに田植えを行い、日々の草刈りから収穫まで、地域のみなさんと一緒に行う予定とのこと。
米澤酒造が大切にしてきた「地域循環」の考えは、伊那食品工業グループの一員になってからも変わらずに引き継がれています。
地元を愛し、お客様とともに歩む
事業継承から4年が経った2018年には、「IWC(インターナショナル・ワイン・チャレンジ)」SAKE部門 純米大吟醸酒の部で、「今錦 年輪 純米大吟醸」がゴールドメダルを受賞。2022年には、「フェミナリーズ世界ワインコンクール2022」で、純米大吟醸の部、純米吟醸の部、純米酒の部の3部門で金賞を受賞しました。

しかし、受賞はあくまで結果であり、目的ではありません。松下さんは、お客様への感謝を次のように語ります。
「米澤酒造の造る日本酒は、愛してくださるお客様のためにあります。事業継承後に設備を少しずつ変えていく過程では、きっと味わいが不安定になったこともあったでしょう。それでも、ずっと温かく見守ってくださり、本当にありがたいです。私たちが目指すのは、常にベストを尽くして、おいしい酒を造ること。そこからすべてが循環していくのだと思っています」
設備をはじめ、変えるべき部分には手を加えながら、新体制で酒造りを続けてきた米澤酒造。しかし、蔵の礎となる製法や味わいの輪郭、そして、地元を愛し、お客様とともに歩む姿勢は変わっていませんでした。
これらが変わらずにあるからこそ、米澤酒造は今も地元のみなさんに愛されているのではないでしょうか。
(取材・文:藪内久美子/編集:SAKETIMES)
sponsored by 米澤酒造株式会社




