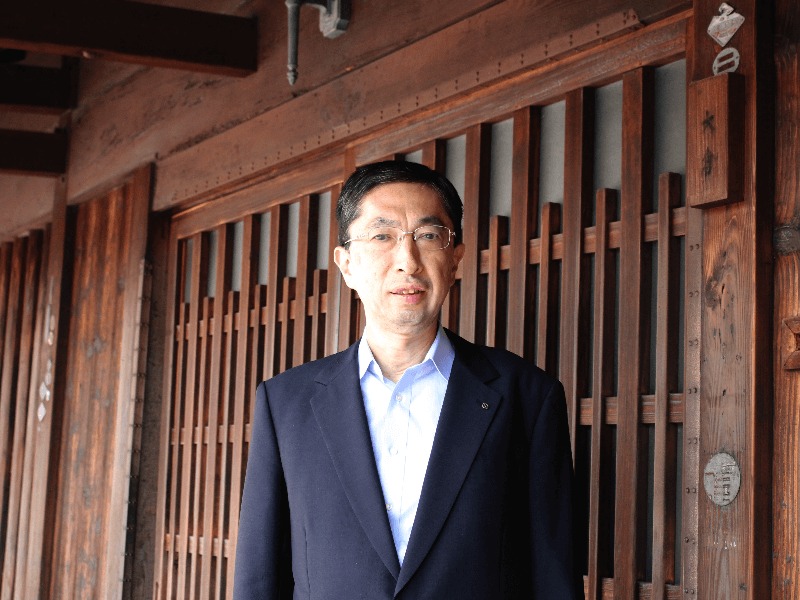『QUALITY・CREATIVITY・HUMANITY』を基本理念に、高い技術力で消費者ニーズに寄り添った商品を提供し続けてきた「月桂冠」。2017年に創業380年、会社設立90周年の節目を迎えたこの一大メーカーについて、そこで働く職人たちの情熱やこだわり、そして海外における日本酒の可能性を切り拓いた米国月桂冠の姿を、シリーズ連載で追ってきました。

今回は、月桂冠の14代当主であり、代表取締役社長を務める大倉治彦氏にお話をうかがいます。
月桂冠の伝統はいかにして培われ、革新されていったのか。話題は、今後の日本酒業界に対する展望や、大倉氏の人となりについてもふくらんでいきました。そんなインタビューを、前後編の2回に分けてお届けします。
月桂冠をさらに100年続けるために
1637(寛永14)年に創業した月桂冠。その歴史は、現在も本社を構える京都・伏見に、初代・大倉治右衛門が開いた酒屋から始まります。月桂冠は、京都で勃発した戦乱や戦災、幾多の苦難を乗り越えながら、革新的な事業や新技術の導入などに取り組み続けてきました。
たとえば、1961(昭和36)年に日本初の四季醸造システムを備えた酒蔵を新設。1984(昭和59)年には、常温で流通できる「生酒」を日本酒業界で初めて販売しています。2008(平成20)年に発売された、日本酒として初の「糖質ゼロ」商品は記憶に新しいところでしょう。
現当主の大倉治彦氏は、一橋大学を卒業後、第一勧業銀行(現・みずほ銀行)へ入行。1987年に月桂冠へ入社しました。1997年から代表取締役社長に就任し、月桂冠を導く14代目として経営にあたっています。
また、日本酒造組合中央会をはじめ、京都経済同友会の代表幹事、商工会議所や工業会でも要職を務め、さらには地元スポーツチームの後援会にも所属。実業家として多忙な日々を送っています。
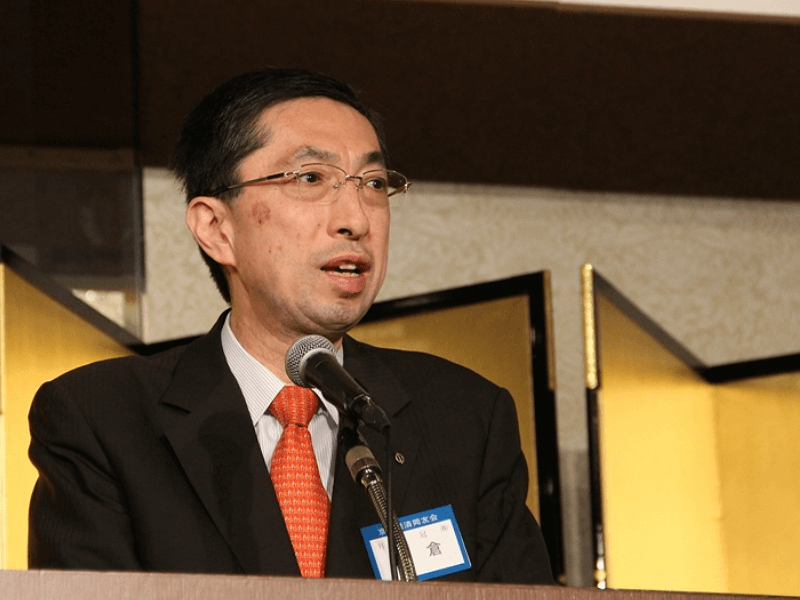
一般消費者向けの商品を中心に、全国へと販路を広げることで月桂冠の基礎を築き上げてきた、12代目・大倉治一氏や13代目・大倉敬一氏から当主を受け継いだ治彦氏。
継承には、先祖代々伝わる"虎の巻"が伴うイメージもありますが、「先代が具体的な文章にしたものはまったくない」のだとか。しいて言うならば、受け継いだのは"生き方そのもの"だと言います。
「親から子へ受け継ぐ場合、仕事のやり方は10年以上いっしょに働くなかで自然とわかってくるもの。むしろ、仕事の具体的な内容は些細なことで、重要なのはもっとコアな部分なのです。たとえば、"謙虚じゃなきゃいかん"とか、"嘘をついたら駄目"だとか、"質素倹約でいるべきだ"とか。また、家庭はもちろん、業界や地域との付き合いを大切にすることも重要ですね。
それはすべて、月桂冠をさらに100年続けたいと思っているからです。
この会社は自分の代で終わりだと思っているのなら、思いきり遊び倒したり、家庭を顧みなかったりすることだってできるかもしれません。そういう経営者で会社が絶好調という人もいるので、なんとも言えませんが......(笑)
ただ月桂冠は、自分だけでなく子どもや孫たちがちゃんと経営していくことで、100年先まで続いていく会社にしたいと考えています。極端に言えば、みずからの行動は子どもにすべて見られているので、"その子がどういう経営者になるのか"まで考えて、行動を律しなければならないということでしょう」
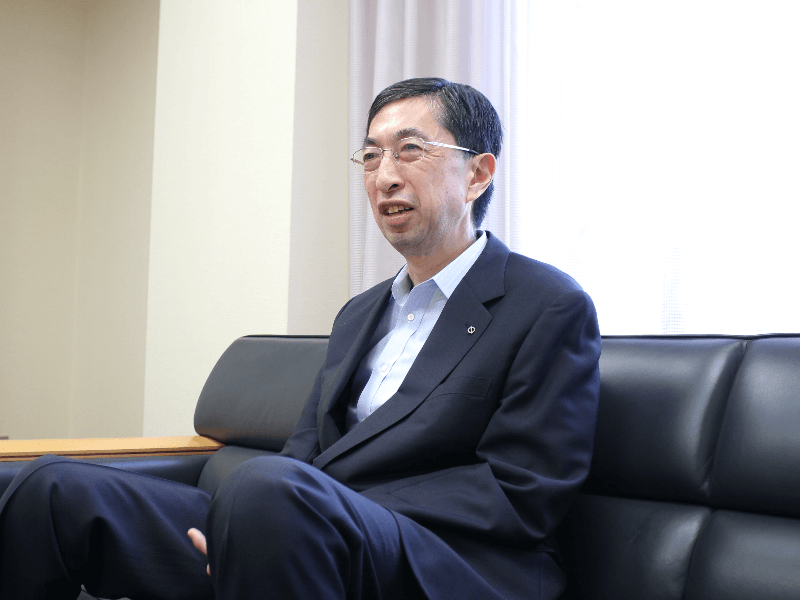
「なかなかできることではありませんよね」と私たちが思わず口にすると、「それをやっておかないと、14代も続かないんですよ」ときっぱり。
大倉氏の曾祖父の代までは、酒蔵兼居宅の"職住一体"で月桂冠を経営していたのだとか。冬になると杜氏や蔵人が大挙し、社員とともに酒造りに携わり、店員が小売販売するのを支える。そんな先代たちの堅実かつ誠実な働きぶりを伝え聞きながら、大倉少年も育っていったのでしょう。
月桂冠が「蔵元杜氏」の酒造りをしない理由
100年先を見据えた経営に取り組む月桂冠。その思想は、同社の酒造りにもはっきりと表れていました。
現在の月桂冠では、生産や営業の現場において、社長がなにか意見をすることは少なく、最終的な判断は各担当責任者に委ねられているのだそう。一方で、昨今の日本酒業界を見ると、経営者みずからが酒造りに関わるメーカーも増えてきています。
通常、酒蔵では、蔵元が杜氏に酒を造ってもらう伝統があったことを背景に、現状の酒造りに対してひとつの見解を示してくれました。

「父の世代だったら、経営者自身が勉強してみずから酒を造ることはしない方がいいとみなが口をそろえて言ったでしょう。もし自分で酒造りをするなら、他人の意見に耳を傾け、市場動向を調査して常に謙虚でいなければなりません。ですが、オーナーがみずから造りに関わると、周囲の人が強く意見しづらいので、10年単位でみると袋小路にはまってしまう可能性があるんです」
しかし現在、蔵元杜氏が多くいるのも事実です。そのことについて「造り手の世代が代わり、古色蒼然とした空気は変わってきていますよね」と明るい声色で話す場面もありました。それは、"日本酒はこうでなければならない"という制約から、造り手が解放され始めていることの表れともいえるでしょう。
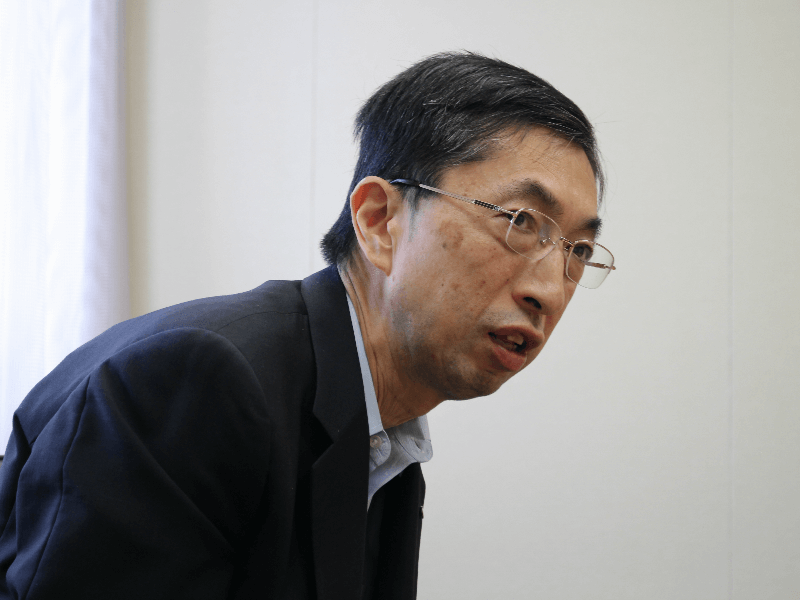
大倉氏も「特に若い蔵元の皆さんには、ルールや慣習にしばられず自由にやってほしいと思いますね」と大きく構えていました。
基本理念の浸透が、酒にも人にも表れる
日本酒を取り巻く環境は、うねりを上げるように変わり続けてきました。少子高齢化をはじめ、コンビニやスーパーマーケットなどが対象になった酒類販売の自由化、特定名称酒の伸張と"地酒ブーム"......日本酒全体の売上が落ち、普通酒の消費量が少しずつ減少している現状で、その煽りをもっとも強く受けているのが、大手や中堅の酒造メーカーです。
そんな逆風の最中にありながら、月桂冠は長きにわたり、日本酒シェア全体の7~8%を押さえ続け、確固たる地位を築いてきました。会社設立の1927(昭和2)年から今日までの90年の間で、赤字になったのは、経営の全社的な見直しを行った2002(平成15)年度の一度だけで、それ以外は安定した収益を確保し続けています。

ここで、ふだんはどんな仕事をしているのか、聞いてみました。
「社長になると、ハンコを押すような雑用の仕事が多いものですよ(笑)。営業や製造の具体的な業務については社員に任せていますから、私は管理部門や総務、人事、経理の仕事が主ですね」
涼しい顔で答えてくれた大倉氏。実は、社長就任時に大きな仕事をひとつ成し遂げているのです。
それは、月桂冠が事業を継続するなかで培ってきた暗黙知の価値観を『QUALITY・CREATIVITY・HUMANITY』という基本理念として言語化したこと。それぞれの理念を言い替えるなら、「品質第一」「革新と挑戦」「社員の一生を大切にする」ということだそうです。
シンプルだからこそ力強いこのフレーズは、月桂冠380年の歴史を商品に反映させ、社員のなかにも"文化"として根付いています。大倉氏は、この言葉をどうやって浸透させたのでしょうか。
「なぜ浸透したのかと問われれば、基本理念の話を何度も繰り返し伝えているからだと思います。理念の話というのは極めて漠然とした抽象的な話ですから、繰り返し聞くうちに社員みんなが自分たちなりに消化し、それぞれ解釈してくれているのでしょう」
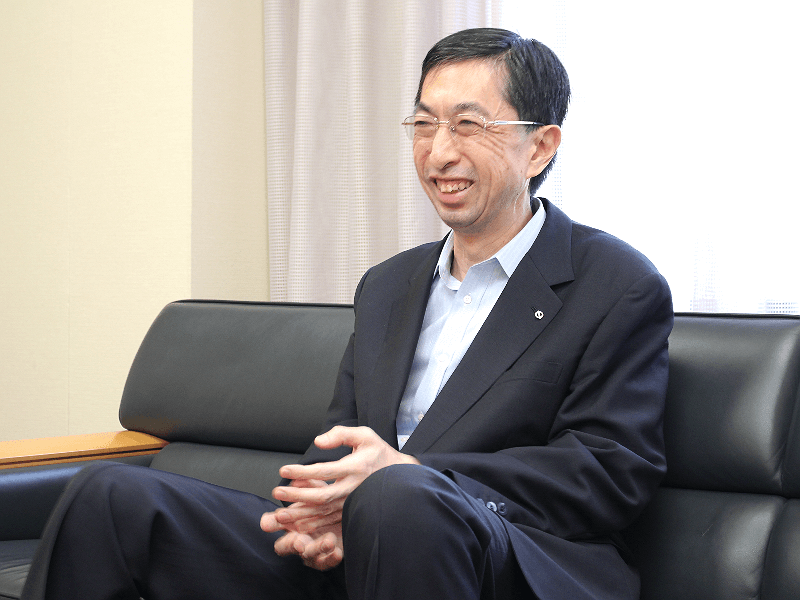
基本理念の解釈が、酒造りに対する情熱や真摯さにもつながっていく。これは、月桂冠の魅力を紐解くキーポイントといえるかもしれません。
インタビューの前半を通して、月桂冠が380年間の歴史で培ってきた、"100年先を見据えた経営"の一端を垣間見ることができました。
後編では、米国月桂冠をはじめとした海外展開について、今後の日本酒業界や月桂冠に対する展望をお聞きしていきます。
【後編はこちら】
(聞き手/生駒龍史、文/長谷川賢人)
sponsored by 月桂冠株式会社