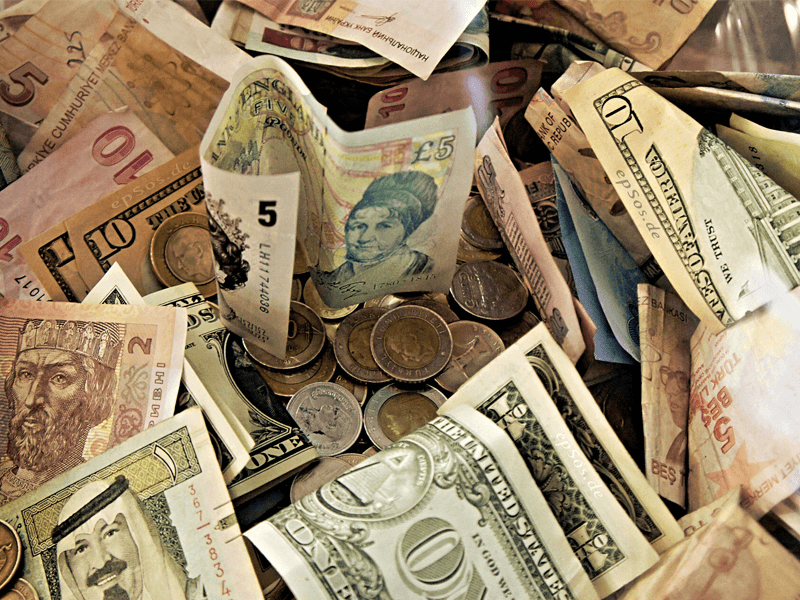江戸時代が幕を閉じ、新しい国づくりを始めた明治政府は、資本主義経済の発達に向けて、大きな舵きりをおこないました。そのうちのひとつが、酒税を国家財政の要としたことです。
「酒の量をごまかす」?!性悪説にとらわれた厳しい徴収
酒税を地租と並ぶ重要な財源とした明治政府が、確実に酒税を徴収するため取った過酷な手段は、想像を絶するものでした。
現在の酒税は、その酒が売れて蔵から出荷される時点で課税する「蔵出税」というものですが、明治時代の酒税は、売れる売れないに関係なく、酒が搾られると同時にその量に対して課税する「造石税」でした。
精米から始まる日本酒造りは、世界中のどの酒にも見られないほど長く複雑な工程で、ワインなどのように「何トンの原料を使えば何トンの酒ができる」といえるものではありません。同じ量の玄米を使って造り始めても、目的とする酒のタイプの違い、杜氏の技術力の差、気候の変動による温度の影響、さらには作業中の不注意による欠損など、最終的に搾られてできる酒の量にはかなりのバラツキが出ます。
しかし、「密造も含めて、蔵元は必ずその量ごまかす」という「性悪説」にとらわれていた政府は、搾った時点の酒の量を計るだけでは信用せず、精米から始まる全ての醸造工程のチェックをしたり、酒の一部をどこかに隠しているのではないかと、蔵中を隅々まで捜査するなど、少しでも不審なところがあれば、徹底的に追求しました。
酒税軽減請願書に取り上げられた悲惨な「十一屋の事件」
常識を逸脱した厳しさは、山梨県酒造組合が明治17年に元老院へ提出した「酒税軽減請願書」の中に見ることができます。本書には「酒造検査は、酒税の高さに苦しむだけではなく、その検査の仕方により苦しめられる」「密造を疑って、蔵の中はもちろん屋敷中を捜索するだけではなく、時にはそれが近隣にも及び、関係者ばかりではなく多くの人々の生活を乱し、疲労困憊させる」と述べた上で、山梨県甲府柳町の酒造家野口忠蔵の「十一屋の事件」を取り上げています。
密造の疑いが掛けられた十一屋に対し、2月4日突然数名の税務職員が同家に出張。その年の仕込みもろみ40本(約千石=18万ℓ)を検査したところ、8斗6升(約155ℓ)の不足を見つけました。もろみ45石(8,100ℓ)弱も搾れば、1石(180ℓ)程度のもろみが減ることはよくあることであるにもかかわらず、税務官吏はこれを密造の疑いがあるとみなしたようです。連日のごとく何人もの官吏が出張してきては、家宅捜索と称し、ふすまを倒し畳をめくるなど、ほとんど足の踏み場もないほどの乱暴を極めたそう。この狼藉に対し地元有志は弁護士会、商工会議所を通じて、野口家は信用ある旧家で、密造などするはずはないと税務署長に陳情をしたところ、税務署側は逆に本局に応援を求め、その捜索の範囲を八方に広げたとのこと。
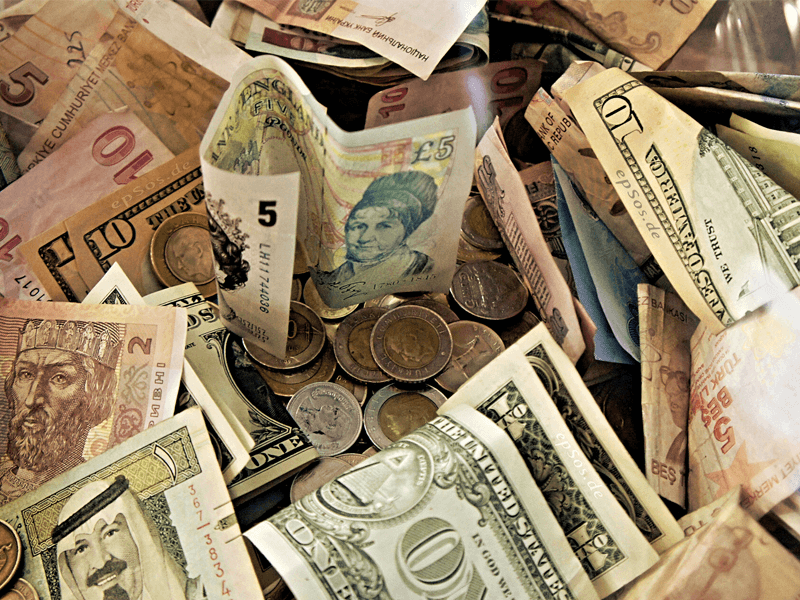
さらには、まだ火入れ(殺菌)をしていない40本(約千石)の新酒の桶全てに封印を張り付け、「こうして半月も置けばたいてい腐ってしまうだろ、後悔するな」と捨て台詞を残して立ち去ったそうです。
税務役人たちはそれでも満足せず、原料米を納入する米屋や酒を売る小売酒屋にまで手を広げ、ある米屋では病気で寝ている老婆の部屋に押し入り「帳簿を抱いて寝ているのだろう」と布団を引きはがしたり、他の米店では「もっとたくさん米を売っただろう」と脅して税務署へ連行し、言語に絶する暴行、脅迫の挙句、字が書けない店主に無理に署名、捺印をさせるなど、乱暴狼藉の限りを尽くしたと言われています。
この事件はその後、山梨県酒造組合が行政訴訟を起こしたり、甲府市民が立ち上がり、新聞社も抗議の市民大会を後押しするなどの結果、1年越しの訴訟は組合側の勝利で落着しますが、その当時の税務官吏の想像を絶する横暴さがよくわかる事件です。
日清・日露の両大戦と引き換えに消えた長期熟成酒
これだけ厳しい酒税の取り立てが行われた背景には、酒造税が地租と共に日本の資本主義の確立・発展を財政的に支える柱と位置づけられたことにあります。容易には上げられない地租に対し、消費税としての弾力性を持つ酒造税は上げやすく、酒造税の全租税収入の中に占める比率は、明治11(1878)年は12.3%であったものが、明治21(1888)年には26.4%へ、更に日清戦争後の明治32(1899)年には、ついに地租の35.6%を抜き去り38.8%にまで拡大しました。これが「日清・日露の大戦は酒税で戦った」と言われるゆえんです。
酒を搾ると同時に課税される過酷な「造石税」は、酒が売れる売れないに関係なくこのように厳しく取り立てられたうえ、貯蔵中に腐敗するリスクも負わなければなりませんでした。そのため、蔵元は一日も早くその酒を売ってしまおうと努力します。結果、酒を熟成させるという概念はなくなり、まして、江戸時代には珍重された、3年、5年など長期間熟成させるという発想は完全に消えてしまったのです。
(文/梁井 宏)